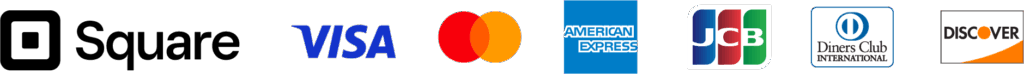目次
1. なぜ今、外国人社員の永住権サポートが重要なのか
少子高齢化を背景とした労働力不足が深刻化する中、専門的なスキルや多様な視点を持つ外国人材は、日本企業の持続的な成長に不可欠な存在となっています。しかし、採用した優秀な人材にいかに長く活躍してもらうかは、多くの企業にとって大きな課題です。
言語や文化の壁、煩雑な行政手続きなど、外国人社員が日本で直面する不安は多岐にわたります。その中でも特に大きな関心事であり、生活の基盤を揺るがしかねないものが「在留資格」の問題です。数年ごとに更新が必要な就労ビザは、常に「日本で働き続けられるか」という不安と隣り合わせであり、長期的なキャリアプランやライフプランを描く上での障壁となり得ます。
この課題に対する解決策の一つが、社員が「永住権」を取得することです。
永住権を取れば、在留期間の更新が不要となり、活動内容にも制限がなくなるため、取得した社員は日本人と同様に、腰を据えて仕事や生活に集中できるようになります。そして、企業がその取得プロセスを積極的に支援することは、単なる福利厚生の提供に留まらず、企業の競争力を高めるうえでの戦略的な人事施策となり得るのではないでしょうか。
この記事では、人事・労務担当者の皆様に向けて、外国人社員の永住権取得を会社がサポートする方法と、それによって企業が得られるメリットについて解説いたします。
2. 押さえておきたい永住権の基本
永住権を取るメリット
一般的に「永住権」と言うことが多いのですが、これは在留資格を持つ外国人が希望する場合に、法務大臣が与える永住許可のことです。永住許可を取得した人のことを永住者と言います。
永住権を取得すると、以下のような大きなメリットがあります。
活動の制限がない
就労ビザの場合は、それぞれの在留資格ごとに、従事することができる業務が決まっています。たとえば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」の場合、資格の取得時に、本人の学歴と業務内容とが合致しているかどうかが厳密に審査されます。もし、そこから外れる業務、たとえば工場での組み立て作業などの現場仕事に従事することは認められません。
しかし、永住権を取得すれば、活動の制限がなくなりますので、日本人と同様に、さまざまな業務をジョブローテーションしながら計画的にキャリアアップをしていくこともできるようになります。
在留期間の制限がない
就労ビザの場合は、最大でも5年というように在留期間に制限があります。したがって、長く働き続けたい場合には、在留期間が切れる前にその都度、更新の手続きを取らなければなりません。
しかし、永住権を取得すれば、在留期間の制限がなくなります。煩雑な更新手続きをしなくてもよくなりますので、これはとても大きなメリットです。うっかり更新手続きを忘れるという心配もなくなります。
3. 永住権が取得できる要件
まずは、永住権を取得するための基本的なルールを理解しておきましょう。法務省の「永住許可に関するガイドライン」に基づき、人事担当者として押さえておくべき4つの主要な要件を解説します。
1. 日本に在留していた期間に関する要件
原則: 引き続き10年以上日本に在留していることが必要
10年のうち、就労資格(例:「技術・人文知識・国際業務」など)または居住資格をもって5年以上在留している必要があります。
「引き続き」という点が重要です。長期間の海外出張や、一度在留資格が切れて再取得した場合などは、在留期間がリセットされる可能性があるため注意が必要です。
特例: 高度専門職は、10年の在留期間が短縮されます。
<高度専門職のポイント制>
これが最も企業と関わりが深い特例です。
・70点以上の場合: 高度人材として3年間継続して日本に在留していること。
・80点以上の場合: 高度人材として1年間継続して日本に在留していること。
(※申請時と、その1年または3年前の時点の両方でポイント計算が必要です)
高度人材ポイントは、学歴、職歴、年収、年齢、保有資格(日本語能力試験N1など)によって算出されます。企業としては、社員がこのポイント制の対象になるかを把握し、該当する場合は早期の永住権取得を後押しできます。
以下の場合にも必要な在留期間が短縮されます。
<日本人・永住者・特別永住者の配偶者>
実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留していること。
<定住者>
「定住者」の在留資格で5年以上継続して在留していること。
2. 素行善良要件
日本の法律を遵守し、社会的に非難されない生活を送っていることが求められます。人事担当者が特に注意すべきは、社員の公的義務の履行状況です。
納税義務
所得税、住民税、法人税(経営者の場合)などを、納期限内に適切に納めているかが厳しく審査されます。たとえ申請時に完納していても、過去に一度でも納期限の遅れがあれば、不許可の要因となり得ます。
社会保険料の納付義務
健康保険料や年金保険料を、納期限内に適切に納めているかも同様に重要です。会社員の場合、給与から天引きされるため問題は起きにくいですが、転職時の空白期間に国民健康保険・国民年金に加入し、その支払いが遅延・未納になっているケースは少なくありません。
これらの公的義務の履行は、永住権審査の根幹をなす部分です。会社として、日頃から適切な給与計算と社会保険手続きを徹底することが、社員の永住権取得を間接的に支える大前提となります。
3. 独立生計要件
公共の負担にならず、日本で安定した生活を送れるだけの資産や技能があることが求められます。
安定した収入
申請者本人または世帯全体の収入が、安定的に継続していることが重要です。審査では、直近5年間(高度人材等の特例の場合は3年または1年)の課税証明書・納税証明書が求められ、年収額とその安定性が評価されます。
年収の目安
明確な基準額は公表されていませんが、一般的に扶養家族の有無を考慮し、年収300万円以上が一つの目安とされています。もちろん、これはあくまで目安であり、他の要素と総合的に判断されます。
企業としては、正社員としての安定した雇用契約や、業務内容に見合った適切な給与水準を維持することが、この要件を満たす上での強力なサポートとなります。
4. 国益適合要件
その外国人の永住が、日本の利益になると判断される必要があります。具体的には、上記の「在留期間要件」「素行善良要件」「独立生計要件」を満たしていることに加え、以下の点が考慮されます。
日本社会への貢献
専門分野での活躍、地域社会への貢献、ボランティア活動などが評価される場合があります。入管の審査官が積極的に調べてくれるわけではありませんので、プラスになると思われる材料があればアピールすべきポイントです。
最長の在留期間
現在保有している在留資格の、最長の在留期間(例:5年や3年)を持っていることが原則として求められます。
最長で5年の在留期間が得られる在留資格であるにも関わらず、1年の在留期間しか付与されていない場合、在留状況が不安定と見なされ、永住申請が認められない可能性があります。
4. 会社ができる永住権取得サポート
永住権の申請は、原則として社員本人が行うものですが、企業が積極的に関与・支援することで、手続きの負担を大幅に軽減し、許可の確実性を高めることができます。ここでは、企業が提供できる具体的なサポート内容を、4つのステップに分けて解説します。
1. 書類作成のサポート
永住権申請には、膨大な量の書類が必要です。その中には、会社でなければ発行できない、あるいは会社の協力が不可欠なものが多数含まれます。
会社発行が必須の書類を迅速に準備する
<在職証明書>
申請者が自社に在籍していることを証明する書類です。フォーマットは自由ですが、所属部署、役職、入社年月日、業務内容などを明記します。
<登記事項証明書、決算報告書の写しなど>
会社の規模や安定性を示すために提出を求められることがあります。特に、比較的小規模な企業や設立間もない企業の場合は重要です。
申請者本人しか取得できない書類の取得を促し、内容を確認する
<課税証明書・納税証明書>
居住地の市区町村役場で取得します。直近5年分(特例の場合は1年または3年分)が必要です。取得漏れがないか、納税に遅延がないかを事前に確認するよう促しましょう。
<公的年金・医療保険の保険料納付状況を証明する資料>
「ねんきん定期便」や「ねんきんネット」の記録、国民健康保険料の納付証明書など、多岐にわたります。会社員期間だけでなく、転職の合間などの国民年金加入期間の証明漏れが起きやすいため、注意喚起が必要です。
任意提出だが、審査に有利に働く書類の作成を支援する
<理由書>
「なぜ永住権を取得したいのか」を本人が記述する重要な書類です。単に「日本が好きだから」といった抽象的な理由ではなく、これまでの日本社会への貢献(仕事の実績など)、今後のキャリアプラン、家族との生活設計などを具体的に記述することが求められます。
会社としては、人事担当者や直属の上司が内容を確認し、「会社の事業にどのように貢献してきたか」「将来的にどのような役割を期待しているか」といった客観的な視点から、より説得力のある内容になるようアドバイスを行うことができます。
<推薦状>
提出は必須ではありませんが、非常に強力なアピール材料となります。
会社の代表取締役、役員、直属の上司などが作成します。
申請者の勤務態度、業務遂行能力、実績、会社への貢献度、将来性、そして誠実な人柄などを具体的に記述します。会社の公印を押印することで、組織としての推薦であることを明確に示せます。この一枚が、審査官にポジティブな印象を与える上で大きな効果を発揮します。
2. 専門家との連携と費用補助
永住権申請は、法律の知識と煩雑な手続きを要するため、行政書士などの専門家に依頼するのが最も確実で効率的です。
信頼できる行政書士の紹介
企業として、外国人材のビザ申請に実績のある行政書士事務所と顧問契約を結んだり、提携関係を築いたりすることで、社員にスムーズに専門家を紹介できます。専門家は、最新の法改正や審査傾向を熟知しており、個々のケースに応じた最適なアドバイスを提供してくれます。
専門家費用の補助制度
行政書士への依頼費用は、十数万円から二十数万円程度が相場です。この費用の一部または全額を会社が負担する制度を設けることは、社員にとって大きな経済的インセンティブとなります。福利厚生の一環として「永住権取得支援制度」を設けることで、企業の魅力を高めることもできます。
3. 身元保証人への対応
永住権申請には、日本人または永住者の「身元保証人」が必要です。
身元保証人の役割
永住申請における身元保証人は、借金などの連帯保証人とは異なり、法的な金銭賠償責任を負うものではありません。保証する内容は、「滞在費」「法令の遵守」「公的義務の履行」といった道義的責任です。万が一、申請者が問題を起こしても、保証人が代わって賠償金を支払う義務はありません。この点を社内で正しく周知することが重要です。
会社役員や上司が身元保証人になるケース
親しい日本人がいない社員にとって、身元保証人探しは大きな壁となります。この際、会社の代表取締役や直属の上司が身元保証人になることは、社員との信頼関係を示す強力なメッセージとなります。
5. サポート体制がもたらす企業のメリット
「技術・人文知識・国際業務」のような就労ビザを持っていれば働くことができるのですから、わざわざ社員のために「永住権」の取得をサポートしてあげる必要はないのでは?そう思われるかもしれません。
しかし、社員の永住権取得を支援することは、単なる福利厚生のためだけではなく、企業の持続的な成長につながる、経営上の大きなメリットにもなります。
メリット1:【人材定着】優秀な人材の流出を防ぎ、定着率を向上させる
これが最大のメリットです。在留資格の更新という数年ごとの不安から解放されることは、社員にとって計り知れない心理的安全性をもたらします。
生活基盤の安定
住宅ローンが組めるようになるなど、社会的な信用が向上し、日本での生活基盤が盤石になります。これにより、社員は安心して家族を呼び寄せ、子どもの教育なども含めた長期的なライフプランを描けるようになります。
帰属意識の醸成
「会社が自分の人生を応援してくれている」という実感は、社員のエンゲージメントとロイヤリティを飛躍的に高めます。「この会社で長く働き続けたい」という強い動機付けとなり、安易な転職を防ぎ、貴重な人材の流出を食い止めます。
メリット2:【採用力強化】「選ばれる企業」としてのブランドを確立する
人材獲得競争が激化する中、外国人材にとって「働きやすさ」は企業選びの重要な基準です。
強力なアピールポイントになりうる
「永住権取得サポート制度あり」という一文は、求人広告において他社との明確な差別化要因となります。特に、日本で長期的なキャリアを築きたいと考える優秀な人材ほど、こうしたサポート体制を重視する傾向があります。
口コミによる好循環
実際にサポートを受けて永住権を取得した社員の満足度は高く、その経験談がリファラル(紹介)採用やSNSなどを通じて広まることで、「外国人を大切にする企業」としてのポジティブな評判が形成され、さらなる優秀な人材の獲得につながります。
メリット3:【管理コスト削減】人事部門の業務負担を大幅に軽減する
外国人社員を雇用する上で、人事部門の隠れた負担となっているのが在留資格の管理業務です。
更新手続きからの解放
就労ビザは1年、3年、5年といった有効期間があり、その都度、出入国在留管理局への更新申請が必要です。会社は、法定調書合計表の写しや在職証明書など、毎回多くの書類を準備しなければなりません。社員が永住権を取得すれば、この煩雑な更新手続きが一切不要となり、人事部門の工数を大幅に削減できます。
メリット4:【事業柔軟性の向上】就労制限がなくなり、人員配置が自由になる
永住権を取得すると、在留資格による活動の制限がなくなります。
キャリアの可能性を拡大
例えば、「技術・人文知識・国際業務」のビザでは、原則として単純労働と見なされる業務に従事することはできません。永住者となれば、こうした制限が撤廃されるため、日本人社員と同様に、本人の適性や希望に応じて、職種の垣根を越えた異動やキャリアチェンジが可能になります。これにより、企業はより柔軟な人員配置戦略を描けるようになります。
経営幹部への登用
就労ビザのままでは役員就任時に「経営・管理」ビザへの変更が必要になるなど複雑な手続きが発生しますが、永住者であればそうした制約もなくなり、経営の中核を担う人材として登用しやすくなります。
6. おわりに:永住権サポートは「未来への投資」
外国人社員の永住権取得をサポートすることは、目先のコストや手間がかかるように見えるかもしれません。しかし、その先には、社員のエンゲージメント向上、離職率の低下、採用競争力の強化、そして管理コストの削減といった、計り知れないリターンが待っています。
それは、多様なバックグラウンドを持つ社員一人ひとりが、在留資格という見えない不安に縛られることなく、持てる能力を最大限に発揮できる環境を整えることに他なりません。
この記事が、貴社で活躍する外国人社員の未来、そして会社の未来を共に明るく照らすための一歩を踏み出すきっかけとなれば幸いです。まずは、社員との面談で「永住権の取得に興味はありますか?」と問いかけることから始めてみてはいかがでしょうか。