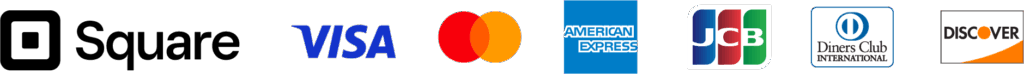日本企業にとって外国人材の活躍は、もはや特別なことではなく、持続的な成長のための重要な経営戦略となっています。その最前線で、採用から受け入れまでを一手に担う人事・採用担当者の皆様の役割は、ますます重要になっています。
しかし、その過程で必ず壁となるのが、在留資格(ビザ)の問題です。特に、エンジニアやマーケター、翻訳担当者といったホワイトカラー人材の採用で広く使われる「技術・人文知識・国際業務」ビザは、適用範囲が広い分、その審査基準は細かく、複雑です。
「内定を出したのに、ビザが不許可になってしまった…」
「どの書類を準備すればいいのか、毎回手探りで不安…」
「自社のケースで、この人材の学歴は本当に認められるのだろうか…」
このような事態を避け、スムーズな受け入れを実現するために、この記事では、人事担当者様が知るべき知識を具体的に解説いたします。
このマニュアルが、貴社のグローバル採用戦略を成功に導く一助となれば幸いです。
目次
1. まず理解すべき3つの柱 – 「技術・人文知識・国際業務」とは?
この在留資格は、3つの異なる専門分野を一つのパッケージにしたものです。採用候補者の職務内容が、このどれに該当するのかを明確に意識することが、すべての始まりです。
1. 「技術」 (Engineer)
自然科学(理系)の分野に属する専門技術・知識を必要とする業務です。
該当する職種例: ITエンジニア、プログラマー、機械設計、建築士、システムエンジニア(SE)、ゲーム開発者など。
求められる知識: 情報工学、機械工学、物理学、建築学などの理系専門知識。
(ポイント)
大学等で関連する理系科目を専攻していることが、最も分かりやすい証明となります。
2. 「人文知識」 (Specialist in Humanities)
人文科学(文系)の分野に属する専門知識を必要とする業務です。
該当する職種例: 企画、営業(海外向け)、マーケティング、経理、総務、法務、人事、コンサルタントなど。
求められる知識: 経済学、経営学、法学、社会学、教育学などの文系専門知識。
(ポイント)
いわゆる「総合職」や「事務職」が広く該当しますが、「誰にでもできる単純作業」と見なされないよう、専門知識をどのように業務に活かすかを明確に説明する必要があります。
3. 「国際業務」 (International Services)
外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務です。
該当する職種例: 翻訳、通訳、語学教師(英会話スクール等)、広報・宣伝、海外取引業務、デザイナー(海外の感性が必要とされる場合)など。
求められる知識: 語学能力はもちろん、その背景にある文化的理解や思考方法。
(ポイント)
この分野のみ、学歴との関連性が薄い場合でも「3年以上の関連する実務経験」があれば認められやすいという特徴があります。(例:大学で専攻は違うが、翻訳家として3年以上活動していた実績がある)
2. 内定を出す前に!採用候補者がビザ要件を満たすかの4ステップ確認
ビザ申請の成否は、採用候補者を選定する段階で、その8割が決まると言っても過言ではありません。内定を出す前に、以下の4ステップを必ず確認してください。
ステップ1:学歴要件の確認
原則として「大学卒業(学士号取得)」または「日本の専門学校卒業(専門士の称号取得)」が必須です。
海外の大学ももちろん対象です。
専門学校の場合は、卒業時に「専門士」または「高度専門士」の称号が付与されていることが重要です。
ステップ2:【最重要】学歴と職務内容の「関連性」の確認
これがビザ審査の心臓部です。本人が大学等で学んだ専門分野と、会社で従事させる職務内容の間に、論理的な繋がりがあることを証明しなければなりません。
◎ 関連性が非常に高い例(スムーズに許可されやすい)
情報工学を専攻 → ITエンジニアとして採用
経済学・経営学を専攻 → 経営企画・マーケターとして採用
英文学を専攻 → 英語の翻訳・通訳者として採用
△ 慎重な説明が必要な例
法学を専攻 → IT企業の海外営業として採用
説明のポイント: 「契約交渉など、法的な素養を活かして海外企業との取引を円滑に進めるために不可欠な人材である」といった形で、学んだ知識がどう業務に活きるかを「採用理由書」で具体的に補足します。
× 関連性の証明が困難な例
体育学を専攻 → 経理担当者として採用
芸術学を専攻 → 機械設計エンジニアとして採用
このような場合は、次のステップ3「実務経験」でカバーできない限り、許可は極めて困難です。
ステップ3:実務経験要件の確認
学歴と職務内容の関連性が低い場合でも、実務経験で補うことが可能です。
「技術」「人文知識」の場合
10年以上の関連する実務経験が必要です。これは非常にハードルが高いです。
「国際業務」の場合
3年以上の関連する実務経験で認められる場合があります。
注意点: いずれも、前職の企業等が発行する「在職証明書」で客観的に証明できる必要があります。
ステップ4:報酬額の確認
外国人であることだけを理由に、不当に低い報酬を設定することはできません。「日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上」であることが法律で定められています。給与水準が、同じ職務内容の日本人社員と比較して妥当であるかを確認してください。
3. 海外在住か・国内在住かによる2つのパターン
候補者の要件確認が済んだら、いよいよ申請手続きです。状況に応じて2つのパターンがあります。まずは流れを見ておきましょう。
パターンA:海外在住者を採用する場合 →「在留資格認定証明書(COE)」交付申請
内定・雇用契約締結: 候補者に内定を出し、雇用契約を締結します。
書類準備: 会社と本人が協力して、第4章で解説する書類一式を準備します。
入管へ申請: 会社の所在地を管轄する出入国在留管理局へ、会社が代理人となって申請します。
審査 (1~3ヶ月): 審査期間はケースバイケースです。
COE交付: 無事に許可されると、紙の「在留資格認定証明書(COE)」が交付されます。
本人へCOE送付: COEを国際郵便等で海外の本人へ送ります。
現地日本大使館でビザ発給: 本人が自国の日本大使館・総領事館にCOEを提出し、パスポートにビザ(査証)のシールを貼ってもらいます。
来日・就労開始: 来日後、空港で在留カードが交付され、就労が可能になります。
パターンB:国内在住者(留学生・転職者)を採用する場合 →「在留資格変更許可」申請
内定・雇用契約締結: 同上。
書類準備: 第4章の書類を準備します。
入管へ申請: 本人の居住地を管轄する出入国在留管理局へ、本人または会社が代理人となって申請します。
審査 (2週間~2ヶ月): COE申請よりは比較的早く結果が出ることが多いです。
許可・新しい在留カード取得: 許可通知のハガキが本人住所に届き、本人が入管で新しい在留カードを受け取ります。
就労開始: 新しい在留カードを受け取った後、正式に就労が可能になります。許可前に働き始めることは不法就労となるため、厳禁です。
4. カテゴリー別・完全必要書類チェックリスト
会社の規模に応じて、提出が免除される書類があります。
自社の「前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」で、源泉徴収税額を確認し、カテゴリーを判断してください。
本人に準備を依頼する書類(全カテゴリー共通)
・申請書(認定証明書(COE)用、または変更許可申請用)
・証明写真(縦4cm×横3cm、3ヶ月以内撮影)→パスポートと同じ写真を使う場合、撮影日の矛盾に注意)
・パスポートのコピー
・履歴書(入管庁のホームページには記載がないのになぜ出すのか?)
・学歴を証明する書類: 大学の卒業証明書(原本または写し)
・(専門学校卒の場合): 専門士または高度専門士の称号を証明する文書
・(実務経験で申請する場合): 前職の在職証明書など、経験年数を証明する文書
・(IT技術者資格に基づいて申請する場合):「情報処理技術」に関する試験または資格の合格証書または資格証書
・(転職者の場合): 前職の源泉徴収票、退職証明書
・(国内在住者の場合): 在留カードのコピー、住民税の課税・納税証明書
会社が準備する書類(カテゴリー別)
【カテゴリー1】上場企業、独立行政法人など
・四季報の写し等、上場を証明する文書
【カテゴリー2】前年の源泉徴収税額が1,000万円以上の企業
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
【カテゴリー3】上記以外の中小企業(多くの企業が該当)
・前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・申請人の活動の内容等を明らかにする資料(労働条件通知書など)
・登記事項証明書
・事業内容を明らかにする資料(会社案内パンフレット、ウェブサイトの写しなど)
・直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)の写し
【カテゴリー4】新設法人など
・申請人の活動の内容等を明らかにする資料(労働条件通知書など)
・登記事項証明書
・事業内容を明らかにする資料(会社案内パンフレット、ウェブサイトの写しなど)
・直近年度の決算報告書(貸借対照表、損益計算書)の写し
・今後1年間の事業計画書
・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
(源泉徴収の免除を受ける機関の場合)
・外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
(源泉徴収の免除を受けない機関の場合)
・給与支払事務所等の開設届出書の写し
・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書
・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
★プロからのアドバイス
カテゴリー3・4の企業や、学歴と職務内容の関連性に少しでも不安がある場合は、「採用理由書」を任意で提出することを強くおすすめします。これは、「なぜ数ある日本人ではなく、この外国人を採用する必要があるのか」を、その人物の専門性と会社の事業を結びつけて、情熱と論理をもって説明する文書です。説得力のある理由書は、審査官の心証を大きく左右します。
5. 申請から来日まで – 入管とのコミュニケーション実務と最終手続き
理論や必要書類を完璧に揃えても、実際の申請プロセスや入管とのやり取りで戸惑うことは少なくありません。この章では、申請書を提出する「その日」から、採用する社員が日本の空港に降り立つ「その日」までの、具体的かつ実践的な流れを解説します。
1. 申請書の提出方法:窓口か、オンラインか?
作成した申請書類一式を、出入国在留管理庁(以下、入管)に提出します。方法は大きく分けて2つあります。
方法A:管轄の入管窓口での直接申請
伝統的な方法です。会社の担当者様、もしくは委任を受けた行政書士が、会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局へ直接出向きます。
どこへ行く?
会社の所在地を管轄する入管です。採用する外国人の居住地ではないので注意してください。(例:本社が東京にあれば、品川にある東京出入国在留管理局)
何を持っていく?
準備した申請書類一式
申請に行く担当者自身の身分証明書(社員証や健康保険証など)
窓口での流れ
到着後、多くの場合、番号札(整理券)を取って長時間待機します。(特に月曜日や、年度末の1月~4月は大変混雑します)
番号が呼ばれ、窓口で書類一式を提出します。審査官がその場で書類が揃っているか形式的なチェックを行います。
不備がなければ書類は受理され、申請番号が記載された**「申請受付票」**が渡されます。この紙は、審査状況の問合せや結果の受領時に必要となるため、絶対に紛失しないでください。
方法B:在留申請のオンラインシステムを利用した申請
2019年から本格的に開始された、インターネット経由で申請する方法です。今後はこちらが主流となるでしょう。
誰が使える?
事前に利用申出の承認を受けた企業の職員や、委任を受けた行政書士などが利用できます。マイナンバーカードとICカードリーダライタが必要です。
メリット
24時間365日、いつでも申請が可能。
入管へ出向く必要がなく、長い待ち時間から解放される。
交通費や移動時間といったコストを削減できる。
流れ
事前に利用申出を行い、IDとパスワードを取得します。
システムにログインし、必要事項を入力、準備した書類(PDF形式)をアップロードします。
申請後、システム上で受付が完了した旨の通知が届きます。
★プロからのアドバイス
初めて利用する際は初期設定に少し手間がかかりますが、今後も継続的に外国人採用を行うのであれば、オンライン申請の体制を整えることをおすすめします。業務効率が劇的に改善されます。
2. 入管からの問合せ対応:もし「追加資料提出通知書」が届いたら
申請後、しばらくすると入管から連絡が来ることがあります。その多くは、審査を進める上での疑問点や、追加で確認したい事項に関するものです。
連絡方法
郵送で「資料提出通知書」という文書が届くのが一般的です。稀に、電話で簡単な確認が入ることもあります。
通知書の内容
「申請者〇〇の件について、以下の資料を追加で提出してください」といった内容で、具体的な書類名(例:職務内容について、より詳細な説明書)や提出期限(通常1~2週間程度)が記載されています。
通知書が届いた場合の対応
「慌てない」ことです。
これは不許可通知ではありません。むしろ、入管が許可に向けて真剣に審査をしてくれている証拠であり、疑問を解消するチャンスです。
なぜこの資料が求められているのか、入管の「意図」を考えましょう。(例:「職務内容の説明書」を求められた→申請書の説明だけでは、学歴との関連性が判断できなかったのかもしれない)
迅速かつ誠実に対応することが大事です。提出期限が書かれていますので、提出期限は厳守です。万が一遅れそうな場合は、必ず事前に電話で連絡し、指示を仰ぎます。求められた資料だけを提出するのではなく、必要であれば補足の説明書(理由書)を自主的に作成し、審査官の疑問を完全に解消するよう努めましょう。
曖昧な回答は避けましょう。電話での問合せがあった場合も同様です。その場で不明な点は「確認して、折り返しご連絡します」と伝え、必ず正確な情報に基づいて回答してください。
3. 許可通知:在留資格認定証明書(COE)の交付方法
無事に審査が完了し、許可となると、入管から許可通知が届きます。この通知方法とCOEの受け取り方が、窓口申請かオンライン申請かによって大きく異なります。
【窓口申請の場合】紙のCOEを直接受け取る
・郵送で届く:許可されると、会社(申請代理人)宛てに「交付通知書」というハガキまたは封書が郵送で届きます。
・入管へ出頭:担当者は、この通知書と身分証明書、申請受付票を持って、再度、申請した入管の窓口へ行きます。
・窓口で受領:窓口で、A4サイズの紙の「在留資格認定証明書(COE)」の原本を受け取ります。
★プロからのアドバイス
受け取ったCOEには「交付年月日」が記載されています。この日から「3ヶ月以内」に、本人が日本に入国しなければ、そのCOEは無効になってしまいます。受領後、速やかに次のステップに進んでください。
【オンライン申請の場合】メールで電子COEが交付される
オンライン申請の最大のメリットの一つが、この交付プロセスにあります。
・メールが届く: 許可されると、在留申請オンラインシステムに登録したメールアドレス宛に、件名が「電子在留資格認定証明書の交付について」といった内容のメールが届きます。
・メールが証明書:メール本文には「在留資格認定証明書番号」とともに、在留資格や在留期間などが書かれており、在留資格が取得できたことがわかります。書かれている内容と、申請した内容とが合っているどうかを確認してください。
このメールが在留資格認定証明書そのものになりますので、大切に保存してください。
★プロからのアドバイス
この「電子在留資格認定証明書」は、従来の紙のCOEと法的に全く同じ効力を持ちます。この制度により、以下のメリットが生まれます。
・入管へ受け取りに行く手間がゼロに: 交付のためにわざわざ入管へ出向く必要がなくなります。
・海外への郵送が不要に: これが最大の利点です。受け取ったメールは、そのまま海外の本人へ転送すれば完了です。EMSやDHLを手配する必要がなくなり、時間とコストを大幅に削減できる上、郵送中の紛失リスクもありません。
4. COEの送付から本人の来日までの最終ステップ
ここからは、海外にいる本人との連携が重要になります。
ステップ1:本人へCOEを送付
【窓口申請(紙)の場合】: EMS(国際スピード郵便)やDHLなど、追跡可能な国際宅配便で、COEの「原本」を本人へ送付します。
【オンライン申請(電子)の場合】: 「電子在留資格認定証明書」のメールを本人に転送します。本人は、そのデータを自身のスマートフォンやタブレットに保存するか、プリンターで印刷しておきます。
ステップ2:本人が自国の日本大使館・総領事館でビザ(査証)を申請
本人は、受け取ったCOE(紙の原本、またはメールが表示された画面や印刷した電子COE)と自身のパスポート、写真、その他大使館が指定する書類を持って、ビザ申請を行います。
ステップ3:パスポートにビザ(査証)シールが貼られる
このビザが、日本へ入国するための「推薦状」の役割を果たします。
ステップ4:航空券の手配と来日
ビザが発給されたことを確認してから、航空券を手配します。
来日当日、空港の入国審査カウンターで、パスポート(ビザが貼られたもの)と在留資格認定証明書(COE)を係官に提示します。
ステップ5:在留カードの交付
成田、羽田、関西、中部、新千歳、広島、福岡の各空港では、入国審査時にその場で顔写真付きの「在留カード」が交付されます。その他の空港などから入国した場合は、居住地の市区町村に住民登録をしたのちに、自宅あてに郵送で届きます。
【重要な注意点】: この時、入国審査官にパスポート(ビザが貼られたもの)と一緒に、COE(紙の原本、または印刷した電子COE/スマホ等での画面提示も可)を提示する必要があります。本人には、忘れずに持参するよう、強く念押ししてください。
ステップ6:来日後の最終手続き
会社の担当者として、最後に本人に案内すべき重要な手続きが「住民登録」です。
本人は、日本での居住地を定めてから14日以内に、その市区町村の役所へ行き、在留カードを持参して住民登録を行う必要があります。
この手続きが完了すると、在留カードの裏面に住所が記載されます。これが完了して、ようやく日本での生活基盤が整ったことになります。
6. 入社後の手続きと管理
入社後の管理も担当者の重要な仕事です。
入社後の届出
外国人社員が入社・退社した際は、14日以内にハローワークへの届出(雇用保険被保険者資格取得届、または雇用状況届出書)と、出入国在留管理庁へのオンライン届出(中長期在留者の受入れに関する届出)を行いましょう。
職務内容の変更に注意
入社後、本人のキャリアアップに伴い職務内容が大きく変わる場合(例:エンジニア → マネジメント専門職)、許可された活動範囲から外れる可能性があります。その際は「就労資格証明書」を取得して現在の仕事が問題ないかを確認したり、場合によっては在留資格の変更を検討したりする必要があります。
更新への備え
許可される在留期間は5年、3年、1年、または3か月となります。許可された在留期間が過ぎてしまうと日本で働くことができなくなってしまいますので、会社側で「誰の在留期間がいつまでなのか」を管理しておき、更新のタイミングが近づいてきたら本人にリマインドすることをおすすめします。本人に代わって会社が手続きを取ることも可能です。
なお、更新申請時には、日本での納税状況が厳しくチェックされます。入社時から、住民税の納付など、公的義務をきちんと果たすよう本人に指導することも、会社の重要な役割になってきます。
7. トラブルシューティング&FAQ
Q1. 新設法人ですが、ビザは取得できますか?
A1. 可能です。ただし、事業の安定性・継続性を証明するために、説得力のある「事業計画書」が不可欠です。事務所の賃貸借契約書や、資本金の証明など、事業の実態を客観的に示す書類をしっかり揃えましょう。
Q2. 雇用契約ではなく「業務委託契約」でも大丈夫ですか?
A2. 原則として不可能です。この在留資格は、特定の機関との継続的で安定した「雇用契約」が前提です。フリーランスとして活動したい場合は、「経営・管理」ビザなど別の選択肢を検討する必要があります。
Q3. 不許可になってしまいました。もう一度申請できますか?
A3. 可能です。まずは入管に出向き、不許可になった理由を具体的に確認することが重要です。理由が分かれば、その問題点をクリアする資料を追加したり、説明を補強したりして再申請することができます。諦める前に、専門家へ相談することをお勧めします。
8. 専門家に依頼するという選択肢も
外国人材の採用と受け入れは、単なる手続きの連続ではありません。それは、多様な才能を組織の力に変え、企業を次のステージへと導くための戦略的な人事活動です。
このマニュアルが、その複雑なプロセスを乗り越えるための羅針盤となり、担当者の皆様の不安を少しでも解消できれば、これに勝る喜びはありません。
それでも、もし手続きに少しでも不安を感じたり、本業に集中するために煩雑な手続きを任せたいとお考えの場合は、入管業務の専門家である行政書士に相談してみることもご検討ください。
当事務所では、最新の法改正や入管の審査傾向を踏まえ、最もスムーズかつ確実な方法でビザ取得手続きを進めさせていただきます。
相談は無料で承っております。相談してみた結果、「やはり自分でやることにした」「他の事務所に頼むことにした」となっても大丈夫です。あとからお電話やメールで勧誘することもありませんので、安心してご相談ください。
貴社が優秀な外国人材を迎え入れることができ、ますます発展されますことを心よりお祈り申し上げます。