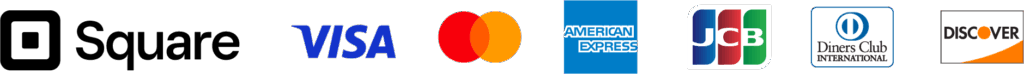相談者:人事部採用担当者
相談者:人事部採用担当者
奥さんと二人暮らしの外国人従業員から相談を受けています。奥さんが妊娠をしたそうなのですが、夫婦二人とも外国人のため、近くに親御さんがいなくてとても不安を感じているようです。そのため、奥さんのお母さんに一時的に日本に来てもらって、一緒に住んでもらいたいと思っているそうです。こういうことは可能なのでしょうか?
 回答者:行政書士
回答者:行政書士
外国人従業員の方が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格で働いていらっしゃる場合、配偶者や子を「家族滞在」という在留資格で呼ぶことは可能なのですが、親御さんとなるとちょっと難しいかもしれませんね。ただし、もしその従業員の方の在留資格が「高度専門職」なのであれば、親御さんを呼ぶことができるかもしれませんよ。
企業のグローバル化が進む中で、多くの日本企業が海外から優秀な人材を積極的に採用しています。その際、採用候補者から必ずと言っていいほど尋ねられるのが、「家族を日本に連れてくることはできますか?」という質問です。
この「家族」という言葉が指す範囲は、配偶者や子だけでなく、時には高齢の親や、本国で長年雇用している家事使用人にまで及ぶことがあります。
在留資格(ビザ)制度は、帯同できる家族の範囲を厳格に定めており、担当者がそのルールを正確に理解していないと、候補者に誤った期待を抱かせてしまい、後々のトラブルに繋がりかねません。
この記事では、主要な就労ビザごとに、どの範囲の家族まで帯同が可能なのか、そのための条件や手続きは何かを分かりやすく解説いたします。
目次
1. 家族帯同の要となる在留資格「家族滞在」とは?
まず、多くの就労ビザで配偶者や子を帯同させるための基本となる在留資格「家族滞在 (Dependent)」について理解する必要があります。
対象となる「家族」の範囲
配偶者
正式な婚姻関係にあるパートナー。内縁関係や事実婚、同性のパートナーは現行法上、原則として対象外です。
子
実子のほか、養子も含まれます。成人して独立した生計を立てている子は対象外です。
対象とならない「家族」の範囲
親、兄弟姉妹、祖父母など
「家族滞在」ビザでは、親や兄弟を呼び寄せることはできません。 これが日本の在留資格制度の大きな原則です。
家事使用人
いわゆるメイドさんは家族ではありませんので、当然といえば当然ですが、「家族滞在」ビザの対象外です。
「家族滞在」の基本的な要件
扶養関係
帯同する家族は、日本で働く本人(扶養者)からの扶養を受ける必要があります。
扶養者の経済力
扶養者には、家族全員を安定して支えるだけの十分な収入や資産があることが求められます。
活動の制限
「家族滞在」ビザで在留する配偶者や子がアルバイトなどをする場合は、事前に入国管理局から「資格外活動許可」を得る必要があり、原則として週28時間以内の就労に制限されます。
2. 主要な就労ビザと帯同家族の可否
以下に、主要なホワイトカラー向け就労ビザと、帯同できる家族の範囲を一覧表にまとめました。
| 在留資格 | おもな職種例 | 配偶者・子の帯同(家族滞在) | 親の帯同 | 家事使用人の帯同 |
|---|---|---|---|---|
| 高度専門職1号・2号 | 高度な研究者、技術者、経営者 | 可 | 条件付きで可 | 条件付きで可 |
| 技術・人文知識・国際業務 | ITエンジニア、マーケター、翻訳者 | 可 | 原則不可 | 原則不可 |
| 経営・管理 | 会社経営者、役員、管理者 | 可 | 原則不可 | 条件付きで可 |
| 企業内転勤 | 海外支社からの転勤者 | 可 | 原則不可 | 原則不可 |
| 教育 | 中学校・高校の語学教師(ALT等) | 可 | 原則不可 | 原則不可 |
| 特定技能1号 | 介護、建設、外食等の現場労働者 | 原則不可 | 不可 | 不可 |
| 特定技能2号 | 熟練した技能を持つ現場労働者 | 可 | 原則不可 | 原則不可 |
| 技能実習 | 技能実習生 | 不可 | 不可 | 不可 |
配偶者と子は、「特定技能1号」と「技能実習」を除き、ほとんどの専門的な就労ビザで帯同が可能です。
一方、親と家事使用人の帯同は極めて例外的であり、「高度専門職」ビザにおいて条件付きで認められているにすぎません。
なお、永住権を取得しても、親の帯同は基本的に認められません。
3. ケース別に見る帯同の条件と注意点
先ほどの表で、「条件付きで可」や「原則不可」としたケースについて、どのような場合に可能となるのかを詳しく解説します。
最も優遇される「高度専門職」ビザの特例
「高度専門職」ビザは、日本の経済成長への貢献が期待される優秀な人材を呼び込むために設けられた、特別な在留資格です。そのため、家族帯同に関しても他のビザにはない優遇措置が用意されています。
親の帯同が認められるケース
高度専門職外国人本人またはその配偶者のどちらかの親に限り、以下のいずれかの条件を満たす場合に帯同が認められます。該当する在留資格は「特定活動」(高度専門職外国人又はその配偶者の親・特別高度人材外国人又はその配偶者の親)になります。
・高度専門職外国人の7歳未満の子(養子含む)を養育する場合
・妊娠中の高度専門職外国人本人、または妊娠中の配偶者の介助・家事支援を行う場合
<主な要件>
・世帯年収: 高度専門職外国人とその配偶者の合計年収が800万円以上であること。
・同居: 日本において、高度専門職外国人と同居すること。
・対象者: 本人または配偶者どちらかの実親・養親に限られます。
家事使用人の帯同が認められるケース
一定の要件を満たす場合、外国人の家事使用人を1名に限り、日本に帯同させることが可能です。
該当する在留資格は「特定活動」(高度専門職外国人の家事使用人・特別高度人材外国人の家事使用人)になります。
<主な要件>
世帯年収: 高度専門職外国人とその配偶者の合計年収が1,000万円以上であること。
<雇用の形態>
・帯同型
本国で1年以上継続して雇用している家事使用人を、一緒に日本へ連れてくる場合。
・家庭事情型
13歳未満の子がいる、または病気等で配偶者が家事に従事できない等の家庭の事情がある場合。(この場合は、本国からの帯同でなくても雇用可能)
<報酬>
家事使用人に対して、月額20万円以上の報酬を支払う契約であること。
一般的な就労ビザでの「親の帯同」という高い壁
「技術・人文知識・国際業務」などの一般的な就労ビザでは、親の帯同はきわめて難しいのが現状です。これは「家族滞在」ビザの対象外のため、「特定活動」というオーダーメイドのビザでの人道的な配慮が求められるからです。
親の帯同が認められる極めて例外的なケース
・本国にいる親が高齢(70歳以上が目安)かつ重い病気を患っている。
・本国に、他に親を扶養できる親族が一人もいないこと。
・日本にいる本人に、親の医療費や生活費のすべてを支える極めて高い経済力があること。
・日本で親の介護・監護を行う具体的な体制が整っていること。
これらの条件をすべて満たし、客観的な資料(医師の診断書、親族関係の証明書など)で立証できた場合にのみ、人道上の観点から「特定活動」ビザが許可される可能性がありますが、そのハードルはきわめて高いと認識してください。
経営者・管理者等のための「家事使用人」帯同
高度専門職でなくても、「経営・管理」や「法律・会計業務」などの在留資格を持つ一部の富裕層・役職者については、家事使用人の雇用が認められる場合があります。該当の在留資格は、「特定活動」(家事使用人)です。
<主な要件>
・申請人(雇用主)が、日本において13歳未満の子を有していること、または病気等の理由により配偶者が日常の家事に従事することができないこと。
・帯同する家事使用人が18歳以上であること。
・月額20万円以上の報酬を支払うこと。
・原則として、本国から一緒に帯同する(出国前に1年以上継続して雇用している)家事使用人であること。
帯同が厳しく制限される「特定技能」「技能実習」
これらの在留資格は、日本の労働力不足を補う目的で創設されており、日本での「永住」を当初から想定していないため、家族帯同は厳しく制限されています。
技能実習・特定技能1号: 家族帯同は一切認められません。
特定技能2号: 特定技能1号を修了し、より熟練した技能が求められる「2号」へ移行した場合に限り、配偶者と子の帯同(「家族滞在」ビザの取得)が可能となります。
4. 家族滞在ビザ申請手続き
配偶者や子を「家族滞在」ビザで呼び寄せる場合、日本で働く本人が代理人となり、本人の居住地を管轄する出入国在留管理局へ「在留資格認定証明書(COE)」の交付申請を行うのが一般的です。
【主な必要書類】
・在留資格認定証明書交付申請書
・本人(配偶者・子)の写真
・返信用封筒
<扶養者(日本で働く社員)に関する書類>
・在職証明書または営業許可書の写しなど
・住民税の課税証明書及び納税証明書(扶養能力を証明する最重要書類)
・在留カードまたは旅券の写し
<本人との身分関係を証明する以下のいずれかの書類>
戸籍謄本
結婚証明書の写し、または婚姻届受理証明書の写し(配偶者の場合)
出生証明書の写し(子の場合)
※いずれも、外国語で書かれている文書には日本語の訳文を添付する必要があります。
5. 外国人夫婦の間に生まれた子の在留資格は?
日本で働き、生活する中で、子が生まれるという素晴らしいライフイベントを迎えるご夫婦も多くいらっしゃいます。しかし、日本で外国籍のご夫婦の間に子が生まれた場合、日本人の場合とは異なる、いくつかの重要な手続きが必要です。
手続きは大きく分けて「①市区町村役場への届出」と「②出入国在留管理庁への申請」の2つがあり、それぞれに期限が設けられています。この章では、人事担当者様が従業員を適切にサポートできるよう、手続きの流れと注意点を時系列で詳しく解説します。
ステップ1:居住地の市区町村役場への届出
まず、子が生まれたという事実を日本の公的な記録に登録する手続きです。これは期限が非常に短いため、最優先で行う必要があります。
手続き①:出生届
これは、日本で生まれたすべての子に必要な、最も重要な手続きです。
<期限>
子の出生日を含めて14日以内
<届出場所>
一般的には、お住まいの市区町村役場に提出します。
<届出人>
原則として父または母
<主な必要書類>
・出生届: 役所の窓口でもらえます。多くの場合、出産した病院で退院時にもらえる「出生証明書」と一体になっています。
・出生証明書: 医師または助産師が作成します。通常、病院で発行されます。
・母子健康手帳: 届出時に持参し、出生届が受理されたことの証明を記入してもらいます。
・届出人の本人確認書類(在留カード、パスポートなど)
・届出人の印鑑(認印で可)
手続き②:その他の関連手続き
出生届を提出する際に、以下の手続きも同時に行うと効率的です。
<住民登録>
出生届を提出すると、子は親の世帯の住民票に記載されます。
<国民健康保険への加入>
親が会社の健康保険(社会保険)に加入している場合は、会社の担当者(つまり、あなた)を通じて、生まれた子を扶養家族として加入させる手続きを行います。親が国民健康保険に加入している場合は、役所で加入手続きをします。
<児童手当の申請>
日本に住所があり、中学校卒業までの児童を養育している家庭に支給される手当です。所得制限がありますが、多くのご家庭が対象となりますので、必ず申請するよう案内してください。
ステップ2:在留資格「家族滞在」の申請が必要
市区町村への届出が完了したら、次は子の「在留資格」を取得するための手続きです。日本で生まれた外国籍の子は、自動的に在留資格を与えられるわけではありません。
60日問題と30日ルール
出生した子は、特別な手続きなしで出生日から最大60日間は日本に在留できます。
しかし、60日を超えて日本に在留する場合は、出生日から30日以内に、以下の「在留資格取得許可申請」を行わなければなりません。
この「30日以内」という期限を過ぎてしまうと、オーバーステイ(不法残留)にはなりませんが、悪質なケースでは罰金が科されたり、将来の他のビザ申請で不利に扱われたりする可能性があるため、厳守すべきです。
在留資格取得許可申請の手続き
ご両親が「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザで働いている場合、その子は「家族滞在」の在留資格を申請するのが一般的です。
<期限>
子の出生日から30日以内
<申請場所>
申請人(子)の居住地を管轄する地方出入国在留管理局
<申請者>
原則として父または母(法定代理人)
<主な必要書類>
・在留資格取得許可申請書
・写真
・子の出生を証明する以下のいずれかの文書
出生届受理証明書(市区町村役場で発行)
出生届記載事項証明書(市区町村役場で発行)
住民票の写し(出生の事実が記載されたもの)
・扶養者のパスポート(申請時に提示)
・扶養者の職業及び収入を証明する文書
在職証明書
住民税の課税証明書及び納税証明書(直近1年分)
・扶養者の在留カード又は旅券の写し
・質問書: 出生に至った経緯などを記載する書式です。
・住民票
★例外:永住許可申請
もしご両親が二人とも「永住者」である場合、生まれた子は「家族滞在」ではなく、いきなり「永住者」の在留資格を申請することができます。この場合も、申請期限は出生後30日以内です。
ステップ3:自国の大使館・領事館への届出(国籍の確保)
見落とされがちですが、非常に重要な手続きです。
日本は「血統主義」を採用しているため、両親が外国人である場合、日本で子が生まれても日本国籍は取得できません。 子の国籍は、両親の国の法律によって決まります。
そのため、両親は、在日している自国の大使館または総領事館に連絡を取り、出生の報告とパスポートの発行申請を行う必要があります。この手続きを怠ると、子が「無国籍」の状態になってしまうリスクがあります。
6. 外国人社員と日本人配偶者との間に子が生まれた場合は?
グローバル化が進む現代、国際結婚はもはや珍しくありません。貴社で働く外国人社員と、その日本人配偶者との間に子が生まれるケースも増えていくことでしょう。
この場合は、子が「日本国籍」を取得するため、手続きの流れが前章の「外国人夫婦の間に子が生まれた場合」とは大きく異なります。
最大の違い:子は「在留資格」が不要
まず、最も重要な点を理解しましょう。
日本の国籍法は「血統主義」を採用しており、父または母のどちらかが日本人であれば、その子は出生によって当然に日本国籍を取得します。
日本国民であるため、日本に在留するための在留資格は一切不要です。外国人同士の子のように、入管へ在留資格の取得申請を行う必要はありません。これが最大の違いです。
手続きの主な流れは「①市区町村役場への届出」と「②外国籍の親の国の大使館への届出」の2つになります。
ステップ1:市区町村役場への届出(日本国籍の確定)
子の日本国籍を法的に確定させ、戸籍に記載するための手続きです。
<出生届>
外国人夫婦の場合と同様、この手続きは必須であり、期限も同じです。
<期限>
子の出生日を含めて14日以内
<届出場所>
子の出生地、または届出人の所在地(お住まいの市区町村役場)
<届出人>
原則として父または母
<主な必要書類>
・出生届: 病院で受け取る「出生証明書」と一体になっています。
・母子健康手帳
・届出人の本人確認書類(日本人親は運転免許証やマイナンバーカード、外国人親は在留カードやパスポート)
・届出人の印鑑(日本人親の印鑑で可)
手続きのポイント:戸籍への記載
<婚姻関係にある場合>
日本人親の戸籍に、子の名前が記載されます。これにより、子は正式に日本人として登録されます。
<婚姻関係にない場合(未婚の母が日本人)>
母の戸籍に子が記載され、子は日本国籍を取得します。
<婚姻関係にない場合(未婚の母が外国人、父が日本人)>
このケースは注意が必要です。出生届だけでは、子は日本国籍を取得できません。父が子を「認知」する手続き(胎児認知または出生後の認知届)を行うことで、子は日本国籍を取得できます。詳細は法務局や市区町村役場への確認が必要です。
ステップ2:外国籍の親の国の大使館・領事館への届出(重国籍の手続き)
子は日本国籍を取得しましたが、同時に外国籍の親の国籍も取得できる場合があります。これを「重国籍」と言います。
外国籍の親の国の法律によりますが、多くの場合、その国の大使館または総領事館に出生を届け出ることで、その国の国籍も取得できます。
なぜこの手続きが重要か?
<アイデンティティの尊重>
子が、自身のルーツであるもう一方の国の国民であるという証明になります。
<その国への渡航の便宜>
例えば、外国籍の親の母国へ帰省する際に、その国のパスポートでスムーズに入国できるなどのメリットがあります。
手続きの流れ
子が生まれる前から、必要書類や手続きの期限を、在日している外国籍の親の国の大使館・領事館のウェブサイト等で確認しておくことが非常に重要です。国によってルールが大きく異なります。
<出生の届出>
日本の役所で発行された「出生届受理証明書」や「戸籍謄本(子が記載されたもの)」などを翻訳し、必要書類と共に大使館・領事館へ提出します。
<外国のパスポート申請>
国籍の登録が完了したら、その国のパスポートを申請・取得します。
<重国籍に関する注意点:国籍の選択>
日本の国籍法では、重国籍者は原則として20歳に達するまで(18歳以降に重国籍になった場合は2年以内)に、いずれか一つの国籍を選択することが求められています。
まとめ:手続きの比較
| 手続き | 外国人夫婦の間に子が生まれた場合 | 外国人と日本人の夫婦の間に子が生まれた場合 |
|---|---|---|
| 子の国籍 | 外国籍(親の国籍) | 日本国籍(及び、条件により親の外国籍との重国籍) |
| 在留資格の取得 | 必要(出生後30日以内に入管へ申請) | 不要 |
| 市町村への届出 | 出生届(14日以内) | 出生届(14日以内、これにより戸籍に記載) |
| 大使館への届出 | 必須(子の国籍とパスポートを確保するため) | 任意(外国籍も取得する場合) |
このように、親の国籍によって、子の出生後に行うべき手続きは異なります。特に、「在留資格の取得が不要」な場合がある点については、担当者として明確に理解し、従業員に正確に伝えるべき重要なポイントです。
7. おわりに
外国人材の採用において、家族帯同の問題は避けて通れません。
配偶者と子の帯同は、多くの就労ビザで可能であり、企業の担当者はそのための手続きをサポートする体制を整えておくべきです。
一方、親と家事使用人の帯同については、「標準」ではなく、あくまでも「特例」です。特に「高度専門職」ビザの取得が大きな鍵を握ることを理解し、該当する可能性のある優秀な人材には、そのメリットを積極的に伝えていくことが採用競争力を高めるかもしれません。
「家族は呼べます」と安易に答えるのではなく、どこまでの範囲の家族が、どのような条件で可能なのかを正確に伝えることが、採用候補者との信頼関係を築くことにもつながるかと思います。複雑なケースに直面した際には、必ず専門家にご相談ください。
当事務所では相談を無料で承っております。相談してみた結果、「やはり自分でやることにした」「他の事務所に頼むことにした」となっても大丈夫です。あとからお電話やメールで勧誘することもありませんので、安心してご相談ください。