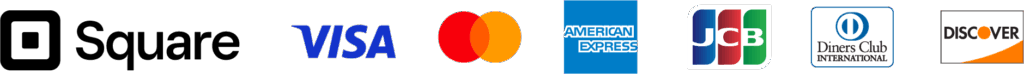2025年10月中旬の施行を目指し、在留資格「経営・管理」(以下、経営管理ビザ)の取得要件が大幅に厳格化される方針が報じられ、日本で起業を目指す外国人に衝撃が走りました。
最も注目されているのは、資本金要件が現行の「500万円以上」から6倍の「3000万円以上」に引き上げられるという点ですが、変更はそれだけにとどまりません。今回の改正は、制度の穴を突いた不正利用を防ぎ、より質の高い、日本経済に真に貢献する経営者を受け入れるという政府の強い意志の表れであり、「量から質への転換」を明確に示すものだと言えます。
令和7年10月10日、実際に入管庁から上陸基準省令の改正が発表され、令和7年10月16日から施行されることが決定しました。
この記事では、経営管理ビザの要件変更について、資本金以外の変更点、厳格化の背景、そしてこれから起業を目指す外国人や、すでにビザを保有している経営者に与える影響などについて解説いたします。
目次
1. なぜ今、大幅な厳格化が必要なのか?改正の背景にある問題点
今回の厳格化の背景には、経営管理ビザ制度が本来の趣旨から逸脱して利用されるケースが増加しているという深刻な問題があります。
① 形骸化していた「500万円」の壁
現行の「資本金500万円以上」という要件は、長年の物価上昇や近年の円安進行により、実質的な価値が大きく低下していました。諸外国の同様のビザ(韓国:約3200万円、米国:約1500万~3000万円)と比較しても著しく低く、「500万円で日本に移住できる」という安易なイメージが広がり、制度の抜け道を探すブローカーの介在や、短期的に資金をかき集めて資本金に見せかける「見せ金」といった手口が横行する一因となっていました。
②「移住目的」のペーパーカンパニーの増加
事業実態のないペーパーカンパニーを設立し、在留資格の取得のみを目的とする申請が後を絶ちません。例えば、民泊経営を掲げて会社を設立したものの、運営は他社に丸投げし、本人は経営に実質的に関与していないケースなどが問題視されています。
③ 社会保障制度への影響
こうした不正なビザ取得は、本人だけでなく、帯同する家族が「家族滞在」ビザで入国し、国民健康保険などに加入することで、日本の医療制度に過度な負担をかける問題にもつながっており、制度の信頼性を揺るがす事態となっていました。
このような状況を是正し、本気で日本で事業を成長させ、雇用を創出し、経済に貢献する意思のある経営者を選別するため、今回の制度改正が急務となったのです。
2. 資本金だけじゃない!厳格化される4つの主要な変更点
今回の改正案は、外国人起業家に複数の高いハードルを課すものです。資本金以外にも、雇用、経営者自身の経歴、そして事業計画の信頼性といった面で、より具体的かつ厳しい要件が求められるようになります。
| 変更前 | 変更後(2025年10月16日以降) | |
|---|---|---|
| 事業規模 | ①資本金500万円以上 または ②常勤職員2名以上 | ①資本金3000万円以上 かつ ②常勤職員1名以上 |
| 経営者の経歴 | 特段の定めなし (管理業務の場合は3年以上の経験) | ①3年以上の経営・管理経験 または ②経営・管理関連の修士号以上 |
| 事業計画書 | 提出は必須だが、 客観的な評価は不要 | 外部専門家(会計士等)による 事業の実現可能性評価が必要 |
| 日本語能力 | 特段の定めなし | 申請者または常勤職員の いずれかに相当程度の日本語能力 |
変更点①:事業規模要件の構造的変更
最大の変更点は、事業規模に関する要件が「選択制」から「必須制」に変わることです。
変更前: 「資本金500万円以上」または「常勤職員(※)2名以上」のどちらかを満たせばよかった。
変更後: 「資本金3000万円以上」かつ「常勤職員1名以上」の両方を満たす必要がある。
これにより、自己資金だけで事業を始めたいと考えていた単独経営者は、資本金を用意するだけでなく、必ず1名以上の雇用を生み出すことが求められます。資本金のハードルが6倍になることに加え、人件費という固定費が初期段階から発生するため、起業の財務的負担は劇的に増加します。
(※常勤職員:日本人、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者のいずれか)
変更点②:経営者自身の能力・経歴の証明
これまでは明確な規定がありませんでしたが、新制度では申請者自身の経営者としての適格性が厳しく問われます。「3年以上の経営または管理の実務経験」か「経営・管理分野の修士号以上の学位」のいずれかを客観的な資料で証明する必要があります。これにより、経営経験のない人物が名義上の経営者となってビザを取得する、といった不正が防止されます。
変更点③:事業計画書の客観性の担保
事業計画書の提出はこれまでも必須でしたが、その実現可能性は入管の審査官が主観的に判断していました。新制度では、中小企業診断士、公認会計士、税理士といった外部の専門家が「事業の実現可能性がある」と評価した書面の添付が求められています。これにより、絵に描いた餅ではない、緻密で客観的に評価されたビジネスモデルが不可欠となります。
変更点④:日本語能力の要求
申請者本人か、雇用する常勤職員のいずれかが、事業運営に支障のない「相当程度の日本語能力」を有することを求められています。これは、日本国内での円滑な事業活動やコンプライアンス遵守を担保する目的があると考えられます。
3. 新制度がもたらす影響と懸念
この歴史的な厳格化は、日本の外国人起業家コミュニティに多大な影響を及ぼします。
① 新規申請者の減少と質の変化
最も直接的な影響は、新規申請者の大幅な減少です。特に、IT、コンサルティング、小規模な飲食店や貿易業など、比較的小資本で起業を目指していた個人事業主やスタートアップにとっては、事実上の「門前払い」となりかねません。
一方で、厳しい要件をクリアできるのは、本国で十分な実績と資金力を持つ企業や、富裕層の投資家などに限られてきます。これにより、日本に設立される外国人企業の平均的な事業規模は拡大し、質は向上すると期待されます。
② 既存ビザ保有者への影響
既に「経営・管理」で在留中の外国人については、猶予措置が取られ、施行日(令和7年10月16日)から3年を経過するまでの間に更新申請をする場合、改正後の基準に適合していなくても、経営状況や改正後の基準に適合する見込み等を踏まえて諾否を判断するとされています。
一方、施行日から3年を経過したあとに更新申請をする場合は、改正後の基準に適合していることが求められます。
なお、施行日の前日までに申請が受け付けされて、審査が継続しているものについては、改正前の許可基準が適用されることになっています。
③「多様な起業」の機会損失にも
政府は「スタートアップ育成5か年計画」を掲げ、イノベーション創出を推進していますが、今回の厳格化は、多様なバックグラウンドを持つ小規模な起業家のアイデアや情熱の芽を摘んでしまうという懸念も指摘されています。資金力だけでなく、独自の技術や斬新なアイデアを持つ人材が日本での起業を諦めてしまうことは、日本経済にとっての機会損失につながる可能性があります。
4. まとめ・日本の外国人起業家政策の大きな転換点
経営管理ビザの要件厳格化は、日本の外国人受け入れ政策が歴史的な転換点を迎えたことを象徴しています。これは、単にハードルを高くするだけでなく、日本がどのような外国人経営者を求めているのかというメッセージと捉えてもよいかもしれません。
これからの日本は、十分な資金力と実現可能なビジネスプランを持ち、日本国内に雇用を創出し、真に日本経済に貢献する「質の高い」起業家を歓迎する姿勢の表れだと思います。この大きな変化の波を乗り越えるために、これまで以上に周到な準備と事業への真摯な取り組みが、すべての外国人経営者に求められています。