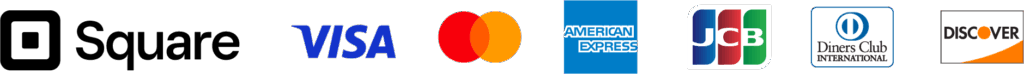相談者:人事部採用担当者
相談者:人事部採用担当者
当社では、4月に日本の大学を卒業予定の留学生を採用したいと考えています。外国人を雇用するのは初めてなのですが、日本人の採用と違って何か特別なことはありますか?また、気をつけたほうがいいことがあったら教えてください。
 回答者:行政書士
回答者:行政書士
基本的には日本人の新卒を採用する場合と大きな違いはありません。ただし、留学生は、日本の学校で勉強する目的で、「留学」という在留資格を取って滞在している外国人ですので、働くための在留資格をあらためて取り直す必要があります。
目次
1. 在留資格の変更が必要
グローバル化が進む現代において、多様な視点を持つ人材を組織に迎え入れることは、企業の成長にとって大きな力となることと思います。
外国人を雇用するのは初めてとのこと。日本人の新卒採用とはどのへんが異なるのか、ご不明な点も多いかと思います。基本的には、日本人の新卒採用と大きく違うわけではなく、日本人と同じように採用活動をしていただいて大丈夫です。
大きく違うところは、採用する留学生が日本で適法に就労するためには「在留資格」(ビザ)を変更する必要があるという点ですね。
この記事では、留学生の採用を決定してから入社に至るまでに企業側が理解しておくべき在留資格の種類、手続きの流れ、そして特に注意すべき点について解説いたします。
2. 留学ビザから就労ビザへ
留学生は、日本の大学などで教育を受けることを目的として「留学」という在留資格で日本に滞在しています。この「留学」ビザは、あくまで学業が本分であり、原則として就労は認められていません。多くの方がご存知の「週28時間以内」のアルバイトは、「資格外活動許可」という特別な許可を得て初めて可能になるものです。
ここで最も注意すべきは、この資格外活動許可は、在籍する大学を卒業した時点でその効力を失うという点です。つまり、卒業後から入社日までの期間、たとえ内定が出ていても、アルバイトとして働いてもらうことはできません。
そのため、卒業後も引き続き日本に滞在し、貴社で正社員として働くためには、現在の「留学」の在留資格を、就労が可能な在留資格へと変更する「在留資格変更許可申請」を、出入国在留管理局(以下、入管)に対して行う必要があります。
この申請は、一般的に卒業を控えた前年の12月頃から受付が開始されます。毎年1月から3月は全国の入管が大変混雑するため、4月の入社に間に合わせるためには、内定後すみやかに準備を開始し、年明け早々には申請を完了させることが理想的です。
3. 取得すべき在留資格の候補
留学生が卒業後に取得すべき就労ビザは、従事する業務内容によっていくつかの種類に分かれます。貴社でどのような業務を任せるかを具体的に想定した上で、最適な在留資格を選択することがとても重要です。
(1)技術・人文知識・国際業務
ホワイトカラーの在留資格として最も一般的で、日本の企業で働く外国人の多くがこの資格で就労しています 。その名の通り、活動内容は以下の3つの分野に大別されます。
•技術:理学、工学など、理系の専門知識を要する業務(例:ITエンジニア、設計開発)
•人文知識:法律学、経済学、社会学など、文系の専門知識を要する業務(例:企画、経理、マーケティング、人事、法務)
•国際業務:外国の文化に基盤を有する思考や感受性を必要とする業務(例:翻訳・通訳、語学指導、海外取引業務、広報・宣伝)
【対象となる業務のイメージ】
複数店舗を統括するエリアマネージャーとしての人材・売上管理、本社でのマーケティング戦略立案、インバウンド顧客向けの広報・企画、海外事業部での貿易実務などが典型例です。
【おもな要件】
•本人:従事する業務に関連する科目を大学(短大含む)や専門学校で専攻し、卒業していること 。または10年以上の実務経験があること 。
•会社:事業の安定性・継続性が認められること。また、日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払うこと 。
【注意点】
この在留資格の最も重要なポイントは、大学での専攻内容と従事する業務内容との間に関連性が求められる点です。また、原則として単純作業は認められていません 。例えば、店舗での接客、レジ打ち、清掃、調理補助といった業務が仕事内容の大半を占める場合は、この在留資格の取得は困難となります。
(2)特定活動46号
これは、日本の大学または大学院を卒業(修了)した留学生を対象とした、比較的新しい在留資格です 。高い日本語能力を持つ留学生が、日本での就職先の選択肢を広げることを目的として創設されました。
【対象となる業務のイメージ】
「技術・人文知識・国際業務」で認められるような専門的業務に加え、その業務の過程で必要となる現場作業にも、ある程度柔軟に従事することが可能です 。例えば、総合職として採用し、将来の幹部候補として育成するために、まずは店舗での接客や商品管理といった現場業務からキャリアをスタートさせる、といった働き方が想定されています。
【おもな要件】
• 本人:日本の大学、大学院、短大、高等専門学校のいずれかを卒業していること 。日本語能力試験N1合格、または大学で日本語を専攻していたなど、高い日本語能力を有していること 。
•会社:日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を支払うこと 。
【注意点】
「技術・人文知識・国際業務」よりも幅広い業務が認められる一方で、あくまで大学で学んだ知識を活かすことが前提です 。厨房での皿洗いや清掃のみに終始するような、専門性との関連が全く見出せない業務は認められません 。また、海外の大学を卒業した留学生は対象外です。
(3)特定技能
深刻な人手不足に対応するため、2019年4月に創設された在留資格です 。特定の産業分野において、一定の専門性・技能を持つ外国人を受け入れることを目的としています。外食業や宿泊業、飲食料品製造業など、2025年7月現在で16の分野が対象です 。
【対象となる業務のイメージ】
例えば「外食業」分野では、飲食物の調理、接客、店舗管理など、店舗運営に関わる幅広い業務に従事できます 。専門学校で調理を学んだ留学生などが、卒業後にこの資格を取得して調理や接客のプロとして働く、といったケースが考えられます。
【おもな要件】
•本人:各分野が定める「技能測定試験」と「日本語能力試験(N4以上等)」に合格していること 。
•会社:各分野の協議会に加盟すること 。外国人材への支援計画を作成し、自社で実施または登録支援機関に委託すること 。
【注意点】
「特定技能」は、大学で学んだ専門知識を活かすというよりは、特定分野における現場の即戦力として活躍することが期待される在留資格です。大学で経済学や経営学を学んだ留学生を、総合職や幹部候補として採用する場合には、あまり馴染まない可能性があります。
4. 採用決定から入社までの手続きの流れ(技術・人文知識・国際業務)
1.内定・雇用契約の締結
採用が決定したら、雇用契約書(または労働条件通知書)を締結します。この際、「本契約は、就労可能な在留資格への変更が許可されることを条件として発効する」といった停止条件付契約にしておくと、万が一不許可になった場合のリスクに対応できます。
2.申請書類の準備
会社と本人、双方が協力して入管へ提出する書類を準備します。
本人が準備する主な書類
・在留資格変更許可申請書、証明写真
・パスポート、在留カード
・大学の卒業(見込)証明書、成績証明書
・履歴書、日本語能力を証明する書類(該当者のみ)
会社が準備する主な書類
・雇用契約書の写し
・会社の登記事項証明書
・直近年度の決算文書の写し
・会社の案内(パンフレット等)
・雇用理由書(申請の経緯や職務内容、本人の能力がどう活かされるかを具体的に説明する書面)
3.入管への申請
原則として本人が居住地を管轄する入管へ出頭し、申請書類一式を提出します。申請取次行政書士に依頼すれば、本人や会社担当者の出頭が免除されます。
4.審査
入管での審査期間は、通常1ヶ月から3ヶ月程度かかります。この間、追加の資料提出を求められることもあります。
5.結果の受領と入社
許可されると、入管からハガキで通知が届きます。本人が入管に出向き、新しい在留カードを受け取れば、手続きは完了です。この新しい在留カードを受け取った後、晴れて貴社の一員として就労を開始することができます。
5. 初めて外国人を雇用する際の注意点
業務内容と在留資格の一致
最も重要な点です。許可された在留資格の範囲を超えた業務に従事させることは「不法就労」となり、本人だけでなく、雇用した企業側も厳しい罰則(不法就労助長罪)の対象となります。
報酬額の妥当性
「日本人と同等額以上」という要件は厳格に審査されます 。貴社の給与規程を明確に示し、不当に低い報酬額でないことを客観的に証明する必要があります。
企業の安定性・継続性の証明
入管は、外国人が安定して日本で生活できるかという観点から、雇用する企業の経営状態も審査します。設立間もない企業や、決算状況が芳しくない場合は、詳細な事業計画書を提出するなど、事業の安定性を丁寧に説明する必要があります。
雇用後の届出義務
外国人を雇用した場合(および離職した場合)は、ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。忘れずに行いましょう。
6. まとめ
日本の大学等を卒業する留学生の採用は、企業にとって大きな可能性を秘めています。しかし、その能力を最大限に発揮してもらうためには、法律に則った適切な手続きを踏むことが不可欠です。
まずは、採用する留学生にどのようなキャリアを歩んでほしいのかを明確にし、それに最も合致した在留資格を選択することから始まります。そして、4月の入社に向けて、余裕を持ったスケジュールで申請準備を進めることが成功の鍵となります。
在留資格の手続きは専門性が高く、複雑な側面もございます。初めてのことでご不安な点が多い場合や、本業に集中するために手続きを円滑に進めたいとお考えの場合は、入管手続きを専門とする当事務所にご相談ください。
入管手続きをご依頼いただきますと、貴社と留学生の方に大きな労力をおかけすることなく、スムーズに申請手続きを進めることができますので、入社前のお忙しい時期に「煩わしい」業務から解放され、本来業務に集中していただけることと思います。