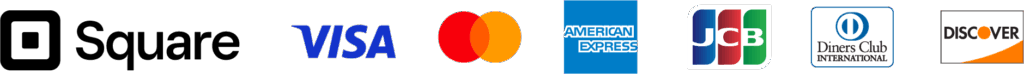相談者:人事部採用担当者
相談者:人事部採用担当者
すでに「技術・人文知識・国際業務」の就労ビザを持っていて転職先を探していた外国人材を採用することになったのですが、会社として何をしたらよいのか教えてください。
とくに知りたかったことは、就労資格証明書を取っておいたほうがいいと聞いたことについてです。そもそも就労資格証明書は、前の会社での業務についての証明であり、転職先の会社でも就労できることを証明するものではないのではないでしょうか?だとすれば、わざわざ取得する必要はないように思いますが、いかがでしょう?
 回答者:行政書士
回答者:行政書士
たしかに、就労資格証明書は、その人が取得している在留資格でどんな業務に就くことができるかを証明するための書類ですので、転職前の就労資格証明書では、転職後の業務をしてもいいかどうかを証明することはできません。そのため、転職したあとに、あらためて就労資格証明書の取得を申請します。その意味は、転職後の仕事であっても「以前と同じ在留資格で働いてもいいですよ」というお墨付きを入管庁からもらっておくということなのです。そうすることで、次の在留資格更新のときに不許可となるリスクを最大限減らすことができます。
外国人の転職者を採用するときに必要な手続き全体の流れと合わせて、詳しく解説いたします。
国内の労働人口が減少する中、専門的なスキルと実務経験を持つ外国人材の中途採用は、企業の競争力を高める上で極めて有効な手段です。特に、すでに「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持って日本で活躍している人材は、即戦力として大きな期待が寄せられます。
しかし、ここで多くの採用担当者様が陥りやすい誤解があります。それは、「すでに就労ビザを持っているのだから、日本人の中途採用と同じで特別な手続きは不要だろう」という思い込みです。
結論から申し上げますと、これは大きな間違いです。
在留資格は、その外国人個人だけでなく、「従事する活動(=仕事内容)」と「所属する機関(=会社)」に対しても許可されています。そのため、転職によって所属機関と仕事内容が変わる場合は、新しい会社として、そして新しい仕事内容として、その在留資格の要件を満たしていることを確認し、法に定められた手続きをしておかなければなりません。
この記事では、採用の内定を出す前の確認事項から、入社後に行うべき法的手続き、そして将来の在留期間更新まで、企業側が担うべき役割と手続きのすべてを、時系列に沿って解説していきます。
目次
1. 内定を出す前の「3つの最重要確認事項」
採用を決定し、内定通知を出す前に、必ず以下の3点を確認してください。これらを怠ると、後々の在留期間更新時に「不許可」という最悪の事態を招き、採用活動そのものが無駄になってしまうリスクがあります。
(1)在留カードの原本確認
まず、採用候補者本人に「在留カード」の原本を提示してもらい、以下の3点を確認します。コピーではなく、必ず原本で確認することが重要です。
在留資格の種類
カード中央の「在留資格」欄が、間違いなく「技術・人文知識・国際業務」となっているかを確認してください。
なお、本人に就労資格証明書の提示を求めて確認をすることもできます。この証明書は、本人からの申請にもとづいて、その人が日本でどんな仕事ができるかを証明するものです。ただし、この証明書がなければ就労できないわけではありませんし、提示しないことを理由に雇用上の不利益な扱いをしてはならないと法律で決められていますので、在留カードで確認が取れれば就労資格証明書まで求める必要はないと思います。
在留期間(満了日)
カード下部の「在留期間(満了日)」がいつまでか。残りの期間が短い場合(例:3ヶ月以内)、入社後すぐに在留期間更新の手続きが必要になることを念頭に置く必要があります。
カードの有効期限
一番下の「有効期間満了日」が過ぎていないか。これは在留期間の満了日とは別に、カード自体の有効期限です。
(2)新しい職務内容との適合性確認
これが最も重要な確認事項です。「技術・人文知識・国際業務」で許可される活動は、専門的な知識や技術を要する業務に限られます。貴社で担当してもらう予定の新しい仕事内容が、この在留資格の範囲内に収まっているかを厳密に確認する必要があります。
適合する例
・A社でシステムエンジニア(技術)として働いていた人を、B社(貴社)でAIエンジニア(技術)として採用する。
・C社で海外マーケティング(人文知識)を担当していた人を、D社(貴社)で海外営業企画(人文知識)として採用する。
適合しない可能性が高い例
・A社で通訳(国際業務)として働いていた人を、B社(貴社)で主に飲食店のホールスタッフや工場でのライン作業に従事させる。
・C社でプログラマー(技術)として働いていた人を、D社(貴社)でその専門性とは関係のない送迎ドライバーや倉庫管理業務に就かせる。
たとえ本人が「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持っていても、新しい仕事内容が単純労働と判断されれば、在留資格の活動範囲外となり、違法就労(不法就労助長罪)に問われるリスクがあります。
(3)本人の学歴・職歴と新業務の関連性
採用候補者が、最初に(前の会社で)「技術・人文知識・国際業務」の許可を得た際には、その方の学歴(大学の専攻など)や過去の職歴と、当時の仕事内容との間に関連性があることが審査されています。
転職後も、その方の学歴・職歴と、貴社で担当する新しい業務内容との間に関連性があるかを確認してください。この一貫性が、将来の在留期間更新の審査をスムーズに進めるための鍵となります。
2. 入社後すぐに会社側が行うべき手続き
上記の確認事項をクリアし、無事に入社日を迎えた後、会社側には法律で定められた、あるいは強く推奨される手続きがあります。
(1)契約機関に関する届出(義務)
こちらは法律で定められた「義務」の手続きです。
届出の内容
「当社の従業員であった〇〇さんが退職しました」または「新たに〇〇さんを雇用しました」という事実を、入管に届け出る制度です。転職の場合、前職の会社が「退職」の届出を、貴社が「雇用(受け入れ)」の届出を行うことになります。
届出の期限
従業員が入社した日(雇用契約が開始した日)から14日以内です。
届出の方法
以下のいずれかの方法で行います。
・オンライン届出:最も推奨される方法です。「出入国在留管理庁電子届出システム」を利用し、インターネット経由で24時間いつでも届出が可能です。
・窓口への持参:会社の所在地を管轄する入管の窓口に、届出書を持参します。
・郵送:届出書を東京出入国在留管理局在留管理情報部門届出受付担当宛に郵送します。
罰則
この届出を怠ったり、虚偽の届出をしたりした場合は、罰金の対象となる可能性がありますので、必ず期限内に行ってください。
(2)就労資格証明書の交付申請(任意)
これは法律上の義務ではありませんが、転職者を受け入れる企業にとって、将来のリスクを回避するために極めて有効な「任意」の手続きです。
就労資格証明書とは?
就労資格証明書は、「この外国人が、この会社で、この仕事内容で働くことは、現在持っている在留資格で認められています」ということを、入管が公式に証明してくれる書類です。
なぜ取得したほうがよいのか?
在留資格証明書は、すでに取得している在留資格について証明するものなのだから、転職先で取得しても意味がないのではないか?と思われるかもしれません。
しかし、ここで取得しておくべき証明書は、転職先の会社での業務と在留資格の適合性を証明するためのものです。
つまり、この証明書は過去を証明するものではなく、未来(転職後)の活動の適法性を、入管が事前に審査し、証明してくれるための手続きなのです。
「お守り」としての重要な役割
もしこの証明書を取得しておかなかった場合、入管が転職後の仕事内容を審査するのは、次回の在留期間更新のタイミングになります。
その時になって初めて「転職後の仕事内容は、あなたの在留資格では認められません」と判断されてしまうと、更新が不許可となり、最悪の場合、会社を辞めて帰国しなければならないという事態に陥ります。
就労資格証明書は、この更新時のリスクをなくすための、いわば「お守り」のようなものです。転職後すぐに取得しておくことで、外国人本人も、受け入れた企業も、安心して次の更新まで働き、働いてもらうことができるのです。
申請のタイミングと場所
入社後、速やかに住居地を管轄する入管に申請します。
主な必要書類
・就労資格証明書交付申請書
・申請人のパスポート及び在留カードの提示
・新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類
3. 「新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類」とは?
入管庁のホームページには、就労資格証明書を取得する際に提出する書類として、「新たな勤務先や活動内容の詳細がわかる書類」と書かれていますが、具体的には何を提出しなければいけないのでしょうか。
具体的には、主に以下の書類を準備する必要があります。
1. 雇用契約書 または 労働条件通知書
これが最も基本的な書類です。新しい会社との間で正式な雇用関係があることを証明します。
目的: 職務内容、役職、給与、雇用期間といった具体的な労働条件を客観的に示します。
ポイント: 給与額が、同じ職務に従事する日本人と同等以上であることが明記されているか確認してください。
2. 会社の登記事項証明書(登記簿謄本)
法務局で取得できる、会社の公式な証明書です。
目的: 会社が日本で法的に存在し、どのような事業を目的として設立されたかを示します。
ポイント: 3ヶ月以内に発行されたものを準備しましょう。
3. 会社の事業内容を明らかにする資料
会社のウェブサイトの会社概要ページを印刷したものや、パンフレット、会社案内などです。
目的: 審査官が、転職先の会社がどのような事業を、どのくらいの規模で行っているのかを迅速に理解するために役立ちます。
4. 職務内容の説明書
これが「活動内容の詳細」の核となる部分です。特に決まった書式はありません。
目的: 転職後、具体的にどのような業務に、どのような立場で関わるのかを詳細に説明します。これにより、その仕事が「技術・人文知識・国際業務」で認められる専門的な業務であり、単純労働ではないことを証明します。
記載すべき内容の例(エンジニアの場合):
担当するプロジェクト名
使用するプログラミング言語や技術
担当する工程(要件定義、設計、開発、テストなど)
チーム内での役割
5. 雇用理由書
必須ではありませんが、提出することが強く推奨される書類です。
目的: なぜ会社がこの外国人を採用する必要があるのか、その方の学歴や職歴が新しい仕事にどう活かされるのかを、説得力をもって説明します。
ポイント: 職務内容の説明書と内容を補完し合い、採用の合理性をアピールする上で非常に重要です。
4. 入管庁以外への手続き
入管法上の手続き以外にも、以下の手続きが必要です。
ハローワークへの届出(外国人雇用状況の届出)
入管への届出とは別に、雇入れの翌月の10日までに管轄のハローワークへ「外国人雇用状況届出書」を提出する義務があります。
社会保険・労働保険の手続き
健康保険、厚生年金保険、雇用保険、労働者災害補償保険(労災)は、国籍を問わず、加入要件を満たす従業員はすべて加入させる義務があります。
5. 次回の在留期間更新許可申請
雇用した従業員の在留期間が満了に近づいたら、貴社が新しい所属機関(雇用主)として、在留期間更新の手続きをサポートすることになります。
申請期間
在留期間満了日の3ヶ月前から申請が可能です。
申請者
原則として外国人本人ですが、会社が手続きを代行することも多いです。
貴社の役割
申請に必要な会社側の書類(前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表、住民税の課税・納税証明書など)を準備し、本人に提供します。
就労資格証明書の効力
先述の「就労資格証明書」を既に入手している場合、この更新申請の際に添付すれば、転職後の活動内容については審査済みと見なされるため、手続きが非常にスムーズに進みます。
6. まとめ
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格を持つ外国人を中途採用する際の手続きは、以下の流れで進めるのが最も安全かつ確実です。
【内定前】 在留カードの原本と、新しい仕事内容との適合性を徹底的に確認する。
【入社後14日以内】 入管へ「契約機関に関する届出」を必ず行う(義務)。
【入社後速やかに】 入管へ「就労資格証明書」の交付申請を強く推奨する(任意)。
【入社翌月10日まで】 ハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う(義務)。
【在留期限3ヶ月前】 会社として書類を準備し、在留期間更新の手続きをサポートする。
これらの手続きを一つでも怠ると、将来的に従業員が日本で働き続けられなくなるリスクや、会社が罰則を受けるリスクが生じます。特に、仕事内容の適合性の判断は専門的な知識を要するため、少しでも不安がある場合は、入管手続きを専門とする当事務所にご相談ください。
相談は無料で承っております。相談してみた結果、「やはり自分でやることにした」「他の事務所に頼むことにした」となっても大丈夫です。あとからお電話やメールで勧誘することもありませんので、安心してご相談ください。