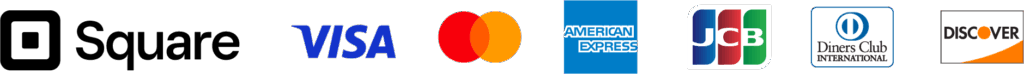DXやAIなどの技術革新を加速させて、グローバルな競争力を獲得する上では、なんといっても優秀なIT人材を獲得することが不可欠となってきますが、経済産業省の調査では、2030年にはIT人材が最大で79万人不足するとも言われており、いかにして優秀なIT人材を採用するかが大きな課題となっています。そういった厳しい状況においては、海外の優秀なITエンジニアを採用するという選択肢は、極めて有効な戦略なのではないでしょうか。
この記事では、外国人エンジニアを採用する際、最も一般的に利用される在留資格である「技術・人文知識・国際業務」について、その全体像から具体的な申請手続き、そして注意すべき点までを網羅的に解説するものです。この記事を最後までお読みいただくことで、採用決定から入社までのプロセスをつかんでいただければ幸いです。
目次
1. 「技術・人文知識・国際業務」とは?
まず、この在留資格がどのようなものかを見てみましょう。
「技術・人文知識・国際業務」は、その名の通り、以下の3つの活動分野をカバーする、専門職向けの代表的な就労ビザです。
・技術 (Engineer):理学、工学、その他の自然科学の分野に属する技術または知識を要する業務。
・人文知識 (Specialist in Humanities):法律学、経済学、社会学、その他の人文科学の分野に属する知識を要する業務。
・国際業務 (International Services):外国の文化に基盤を有する思考または感受性を必要とする業務。
これらのうち、ITエンジニアを雇用する場合には、主に「技術」の分野に該当します。具体的には、システムエンジニア、プログラマー、ネットワークエンジニア、インフラエンジニア、AI開発者、データサイエンティストといった職種が典型的な例です。
重要なのは、この在留資格は「専門的な知識・技術を要する業務」に対して許可されるものであり、単純労働と見なされる業務は対象外であるという点です。
2. 許可を得るための3つの重要要件
「技術・人文知識・国際業務」の許可を得るためには、「① 本人の要件」「② 会社の要件」「③ 業務内容の要件」の3つをすべて満たし、それを客観的な書類で証明する必要があります。
(1)本人の要件(学歴・職歴)
採用候補者である外国人本人が、従事する専門的業務に見合う知識やスキルを有していることを証明する必要があります。
学歴要件(原則)
従事しようとする業務に必要な技術や知識に関連する科目を専攻して、大学(短期大学を含む)を卒業していること、またはこれと同等以上の教育を受けていることが原則です。日本の大学である必要はなく、海外の大学でも問題ありません。
例えば、情報工学(Information Technology)を専攻して大学を卒業した人が、SEとしてシステム開発に従事する、といったケースがこれに該当します。
実務経験要件(学歴要件を満たさない場合)
もし学歴要件を満たさない場合でも、従事しようとする業務について10年以上の実務経験があれば、要件を満たすとされています。この実務経験には、大学や専門学校で関連科目を専攻した期間も含まれます。
IT資格による特例
法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格しているか、資格を保有している場合は、上記の学歴・職歴要件がなくても、この在留資格の対象となります。日本の国家資格だけでなく、一部の海外(中国、フィリピン、ベトナムなど)で実施される試験も対象です。
(2)会社の要件(事業の安定性・継続性)
外国人材を雇用し、安定した給与を継続的に支払うことができる企業であることを証明する必要があります。
事業の安定性・継続性
直近の決算状況が良好(債務超過でないことが望ましい)であり、事業が適正に行われていることが求められます。設立間もない企業の場合は、詳細な事業計画書を提出し、将来にわたる安定性・継続性を客観的に示す必要があります。
適正な雇用契約
外国人本人との間で、雇用契約を締結していることが必須です。契約内容には、業務内容、契約期間、勤務地、労働時間、報酬、退職に関する事項などが明確に記載されている必要があります。
日本人と同等額以上の報酬
外国人であるという理由で不当に低い報酬を設定することは認められません。同じ職務内容の日本人がいる場合、その日本人と同等額以上の報酬を支払うことが法律で定められています。明確な比較対象がいない場合でも、同業他社の同職種の給与水準や、新卒であれば日本の大卒初任給などが一つの目安となります。
(3)業務内容の要件(専門性と関連性)
これが最も重要な審査ポイントの一つです。
専門性と業務内容の一致
本人が大学で学んだ内容や、これまでの職務経験と、これから会社で従事する業務内容との間に、明確な関連性があることが求められます。例えば、大学で文学を専攻した人を、特段の理由なくインフラエンジニアとして採用することは、関連性の説明が非常に困難です。
単純労働ではないこと
先述の通り、許可されるのは専門的な業務です。業務内容の大半が、誰にでもできるような単純作業(例:PCのキッティング作業のみ、データ入力のみ)であると判断された場合、不許可となる可能性が高まります。
3. 【ケース別】申請手続きのフロー
手続きは、採用する外国人が海外にいるか、日本にいるかで大きく異なります。
ケース1:海外在住のエンジニアを採用する場合
この場合、まず日本国内で「在留資格認定証明書(Certificate of Eligibility: CoE)」を取得し、それを本人に送付する必要があります。
【ステップ1】申請書類の準備(約2週間~1ヶ月)
後述する「4.カテゴリー別 必要書類一覧」を参考に、会社と本人の双方で必要書類を収集・作成します。特に海外にいる本人からの書類(卒業証明書など)は、取り寄せに時間がかかる場合があるので、早めに依頼しましょう。
【ステップ2】管轄の入管へ申請
会社の所在地を管轄する出入国在留管理局に、「在留資格認定証明書交付申請書」と集めた書類一式を提出します。
【ステップ3】入管での審査(約1~3ヶ月)
申請後、入管で審査が行われます。審査期間は申請時期や個別の案件によって変動します。審査の過程で、追加の資料提出を求められることもあります。
【ステップ4】在留資格認定証明書(CoE)の受け取り
審査が完了し、許可されると、CoEが交付されます。現在は、紙の証明書のほか、電子メールで受け取ることも可能です。
【ステップ5】本人へCoEを送付
受け取ったCoE(紙または電子データ)を、海外にいる本人へ国際郵便やメールで送ります。
【ステップ6】現地の日本大使館・領事館でビザ(査証)申請
本人は、CoEとパスポート、その他必要書類を持って、自国にある日本の大使館や領事館でビザ(査証)の発給申請を行います。
【ステップ7】来日・入社
ビザが発給されたら、CoEの交付日から3ヶ月以内に来日する必要があります。主要な空港では、入国審査の際にパスポート、ビザ、CoEを提示し、その場で「在留カード」が交付されます。この在留カードを受け取った後、正式に入社し、就労を開始できます。
ケース2:日本在住の留学生などを採用する場合
この場合、現在の在留資格(例:「留学」)から「技術・人文知識・国際業務」へ「在留資格変更許可申請」を行います。
【ステップ1】申請書類の準備(約2週間~1ヶ月)
基本的な必要書類はCoE申請の場合と似ていますが、申請書様式が異なります。本人が現在持っている在留カードの写しなども必要になります。
【ステップ2】管轄の入管へ申請
原則として、本人の居住地を管轄する出入国在留管理局に、「在留資格変更許可申請書」と必要書類一式を提出します。
【ステップ3】入管での審査(約2週間~2ヶ月)
審査期間はCoE申請よりは短い傾向にありますが、これもケースバイケースです。審査期間中、本人は現在持っている在留資格の期限が切れても、特例期間として最大2ヶ月間は適法に日本に滞在できます。
【ステップ4】結果の受領・新しい在留カードの取得
許可されると、入管から通知のハガキが届きます。本人が入管に出向き、手数料(4,000円の収入印紙)を納付して、新しい在留カードを受け取ります。この新しい在留カードには、在留資格が「技術・人文知識・国際業務」と記載されています。
【ステップ5】入社
新しい在留カードを受け取った後、就労を開始できます。
4. カテゴリー別 必要書類一覧
入管への申請では、雇用する会社をその規模や信頼性に応じて4つのカテゴリーに分類しており、カテゴリーによって提出を求められる書類が大幅に異なります。自社がどのカテゴリーに該当するかをまず確認しましょう。
カテゴリー1:日本の証券取引所に上場している企業、保険業を営む相互会社など
カテゴリー2:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表の源泉徴収税額が1,000万円以上の団体・個人
カテゴリー3:前年分の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表が提出された団体・個人(カテゴリー2を除く)
カテゴリー4:上記のいずれにも該当しない団体・個人(新設法人など)
【全カテゴリー共通で必要な書類】
在留資格認定証明書交付申請書(または在留資格変更許可申請書)
写真(縦4cm×横3cm)
返信用封筒(CoEを紙で受け取る場合)
【本人に関する書類】
学歴を証明する書類:卒業証明書、成績証明書など
職歴を証明する書類(該当者のみ):在職証明書など
IT資格を証明する書類(該当者のみ):合格証書、資格者証など
パスポートの写し(CoE申請時)
在留カードの写し(変更申請時)
【会社に関する書類(カテゴリー別)】
カテゴリー1 ・四季報の写し、または日本の証券取引所に上場していることを証明する文書の写し
カテゴリー2 ・前年分の給与所得の源泉徴-収票等の法定調書合計表(写し)
カテゴリー3 ・前年分の給与所得の源泉徴-収票等の法定調書合計表(写し)
カテゴリー4 ・カテゴリー3の書類が提出できない理由を明らかにする資料(源泉徴収の免除証明書など)、給与支払事務所等の開設届出書の写し、直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるものの写し)
【カテゴリー3・4の会社が上記に加えて提出する主な書類】
労働条件を明示する文書:雇用契約書や労働条件通知書の写し
事業内容を明らかにする資料:会社のパンフレットやウェブサイトの写しなど
(カテゴリー4は必須)事業計画書:設立間もない企業の場合、今後1年間の事業計画を具体的に示した書類
(カテゴリー4は必須)会社の登記事項証明書
(カテゴリー4は必須)直近の年度の決算文書の写し
5. 申請の成否を分ける「雇用理由書」の書き方
特にカテゴリー3や4の企業、また学歴と業務内容の関連性が一見して分かりにくい場合には、「雇用理由書」の提出がたいへん重要になります。これは、なぜ他の日本人ではなく、この外国人を採用する必要があるのかを、入管の審査官に分かりやすく説明するための補足資料です。
【記載すべきポイント】
・会社の事業内容と沿革:どのような事業を行っている会社なのかを簡潔に説明します。
・採用の経緯:どのような採用活動を経て、この人材にたどり着いたのかを説明します。
・本人の経歴とスキル:本人が持つ専門知識や技術、実績などを具体的に記載します。
・具体的な職務内容:入社後、どのようなプロジェクトで、どのような業務に、どのような役職で従事するのかを詳細に記述します。(例:「〇〇プロジェクトにおいて、Javaを用いたバックエンド開発を担当」など)
・採用の必要性:本人のスキルが、会社の事業にどのように貢献するのか、なぜその業務に本人が不可欠なのかを論理的に説明します。
この理由書を丁寧に作成することで、提出書類だけでは伝わらない採用の妥当性を補強し、許可の可能性を高めることができます。
6. 申請における注意点とよくある不許可事例
学歴と業務内容の不一致:「経済学部卒の留学生を、プログラミング未経験でSEとして採用」といったケースは、関連性の説明が難しく不許可になりやすい典型例です。
・報酬額が低い:同職種の日本人に比べて明らかに低い、または最低賃金に近いような報酬額は、安定した生活が困難と見なされ不許可の原因となります。
・業務内容が不明確・単純労働の疑い:職務内容の説明が曖昧で、「その他付随業務」などとしか書かれていない場合、単純労働を隠しているのではないかと疑われる可能性があります。
・会社の経営状態:決算が大幅な赤字であったり、債務超過であったりする場合、事業の安定性が認められず不許可となることがあります。
・提出書類の不備・矛盾:申請書の内容と、雇用契約書や会社の決算書の数字が一致しないなど、書類間に矛盾があると信頼性が低いと判断されます。
7. 入社後の手続き
無事に入社が決まった後も、会社として行うべき手続きがあります。
ハローワークへの届出:外国人従業員の雇用保険加入手続きとは別に、入社の翌月10日までに管轄のハローワークへ「外国人雇用状況の届出」を行う義務があります。
各種社会保険の手続き:健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険は、日本人従業員と同様に加入手続きが必要です。
8. 専門家に任せるという選択肢も
外国人ITエンジニアの採用は、書類準備から申請、入社後の管理まで、日本人採用にはない多くのプロセスを伴います。特に初めての場合は、戸惑うことも多いかと思います。
この記事が、採用活動の一助となれば幸いですが、もし手続きに少しでも不安を感じたり、本業に集中するために煩雑な手続きを任せたいとお考えの場合は、入管業務の専門家である行政書士に相談してみることもご検討ください。
当事務所では、最新の法改正や入管の審査傾向を踏まえ、最もスムーズかつ確実な方法でビザ取得手続きを進めさせていただきます。
相談は無料で承っております。相談してみた結果、「やはり自分でやることにした」「他の事務所に頼むことにした」となっても大丈夫です。あとからお電話やメールで勧誘することもありませんので、安心してご相談ください。
貴社が優秀なエンジニアを迎え入れることができ、ますます発展されますことを心よりお祈り申し上げます。