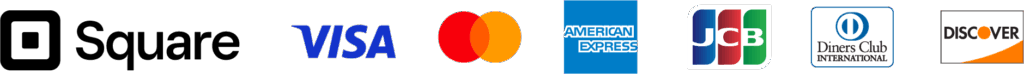「外国人を雇うにはどういう手続きが必要なの?」
「就労ビザってよく聞くけど、結局どういうもの?」
近年、多くの会社が外国人を雇用したいと考えています。
海外の企業との取引を増やしてグローバルな会社にしたい、海外の優秀なIT人材を獲得して技術力を高めたい、日本人だけでは人手が集まらなくて店舗展開に支障が出そうだから外国人を雇いたい、など、業種によっても事情はさまざまです。
でも、いざ外国人を雇用したいと思っても、いったい何から始めたらいいのかわからない、就労ビザという言葉をよく耳にするけれどそれってどういうものなの?と、悩んでしまうことも多いように思います。
この記事では、外国人の雇用をお考えの会社の経営者や担当者の方に向けて、おさえておきたい在留資格の基礎知識から、在留資格を取得するまでの流れを解説していきます。
目次
1. 就労ビザってどういうもの?
「就労ビザ」という言葉を聞いたことがありますか?外国人が日本で働く目的で日本に滞在するためには、この「就労ビザ」を取得しておく必要があります。
ビザと在留資格は別のもの
「就労ビザ」という呼び方はじつは通称です。就労するために必要な「在留資格」のことを、一般的に「就労ビザ」と呼ぶことが多いです。
いわゆる「ビザ(=査証)」は、入国するときに空港などの入国審査の窓口で提示する通行証のようなもののことを言います。これは、その外国人が暮らす国の日本大使館などで受け取ることができます。
就労するためのビザを受け取るためには、あらかじめ、日本国内の出入国在留管理局から在留資格の許可を取っておく必要があります。在留資格を取得したことを証する書類を日本大使館などに提出することで、いわゆる「就労ビザ」を受け取ることができるという仕組みです。
来日時の空港でこのビザを提出すれば、すでに在留資格があることの確認が取れるため、スムーズに入国することができるというわけです。
観光なら日本に入国するためのビザは不要
ちなみに、海外旅行に行くときにビザを取った覚えがないという方が多いですよね。これは、観光目的などの短期間の滞在であれば、お互いにビザを不要としている国が多いからです。
韓国やアメリカなどの主要な国は、日本とお互いに免除することを約束しています。そういった国の外国人が観光で日本にやってくるときはビザを持っている必要がありません。
2. どの在留資格を取ったらいいの?
このような観光の場合と違って、外国人が日本で働く目的で来日する場合には、あらかじめ在留資格を取っておく必要があります。
この在留資格は、外国人本人が申請することもできますが、申請先は日本国内にある出入国在留管理局ですので、外国人を雇用する日本の会社が手続きすることが一般的になっています。
出入国在留管理庁のホームページなどを見ると、さまざまな在留資格があることがわかります。
では、いったい、どの在留資格を取ったらよいのでしょうか。
就労ビザはホワイトカラーと現場作業とで大きく違う
就労することができる在留資格は、高度人材、いわゆるホワイトカラーの仕事と、現場作業の仕事とに分けることができます。
ホワイトカラーの仕事というのは、大学等で学んだ専門知識や長年の実務経験を生かして従事する仕事です。たとえば、ITエンジニアですとか通訳などの仕事がこれに該当します。
一方、現場作業の仕事は、介護施設の介護職員や建設業の作業員、ビルクリーニングの清掃員などが該当します。
ホワイトカラーの在留資格と現場作業の在留資格とでは、資格の取得方法や雇用後に会社がやらなければならないことなどの点で大きな違いがあり、すべてを解説しようとすると膨大な文字数になってしまいますので、この記事ではホワイトカラーの在留資格について解説していきたいと思います。
3. ホワイトカラーのおもな在留資格
ホワイトカラーの在留資格にもさまざまなものがあります。以下がおもな在留資格ですが、高度の知識があって、専門性の高い職業ですね。
| 経営・管理 | 会社の経営者や大企業の管理職など |
|---|---|
| 法律・会計業務 | 弁護士や公認会計士など |
| 研究 | 政府関係機関や企業の研究機関の研究員など |
| 教育 | 中学校、高等学校の語学教師など |
| 技術・人文知識・国際業務 | 日本の企業等に雇用されるIT技術者や通訳など |
| 企業内転勤 | 海外にある支店などからの転勤者 |
ホワイトカラーの代表的な在留資格が「技術・人文知識・国際業務」
さまざまな在留資格がある中で、「技術・人文知識・国際業務」は、ホワイトカラーの在留資格としてもっとも一般的に使われているもので、日本の企業で働く外国人の多くがこの資格で就労しています。
以下が「技術・人文知識・国際業務」の仕事に該当する活動になります。
技術
理学、工学その他の自然科学の分野を専攻し、ITエンジニア、機械設計、プログラマーなど、大学での理系の学問や技術を活かした職種です。
人文知識
法学、経済学、社会学などを専攻し、マーケティング、経理、法務などの職種で活躍できる職種です。
国際業務
通訳・翻訳、語学指導、海外取引・貿易業務など、外国人ならではの語学力や国際感覚を活かした業務です。
4. 技術・人文知識・国際業務の取得で会社に求められる要件
「技術・人文知識・国際業務」の在留資格の外国人を雇用する会社には、求められる要件がいくつかありますので、それらをクリアしていなければなりません。以下がおもな要件です。
基準にあてはまらない仕事をさせることはできない
仕事の内容は、入管の定める活動内容に適合している必要があります。たとえば、ITエンジニアとして在留資格を取得した人に、倉庫作業や清掃などの単純労働をさせることはできません。これは不法就労とみなされ、企業側にも罰則が及ぶ可能性があります。
そして、活動の期間全体を通して適合している必要がありますので、たしかに一部ではITエンジニアとしての活動をしているものの、全体では活動のほとんどが工場の製造ラインでの単純作業といったことは認められません。
日本国内に事務所などがあることが必要
「技術・人文知識・国際業務」の活動の前提として、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う」と定められています。その意味するところは、外国人を雇用するのは、日本国内に拠点のある会社や公の機関等である必要があるということです。外国の会社であっても、日本に事務所や事業所があれば大丈夫です。
雇用契約などを結ぶ必要がある
本人との間で契約を結んでいることが必要です。
必ずしも雇用契約である必要はなく、委任や委託、嘱託などでもかまわないのですが、継続的に働ける内容になっていなければなりません。
日本人と同等以上の報酬でなければならない
雇用する会社が外国人に支払う報酬は、その会社が日本人の従業員に支払う報酬と同等以上のものでなければなりません。報酬には、通勤手当、扶養手当、住宅手当等の実費弁償の性格を有するもの(課税対象となるものを除く)は含みません。
一概には言えませんが、少なくとも、大卒初任給程度以上の金額が最低限の目安となっているようです。
5. 外国人に求められる要件
外国人が在留資格を取得するための要件もいくつかあります。外国人本人については、おもに学歴と職歴です。就こうとしている仕事に対して、それに見合うだけの学歴や仕事の経験があるのかを確認するためです。
学歴の要件
たとえば、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合は、業務に必要な技術又は知識に関連する科目を、大学(短期大学を含む)または専修学校で専攻して卒業していることが必要です。
なお、「大学は、学術の中心として、広く知識を授けるとともに、深く専門の学芸を教授研究し、知的、道徳的及び応用的能力を展開させることを目的とし、また、その目的を実現するための教育研究を行い、その成果を広く社会に提供することにより、社会の発展に寄与する」という大学の性格を踏まえ、大学における専攻科目と従事しようとする業務の関連性については、ある程度柔軟に判断されています。
一方、専修学校は、職業若しくは実際生活に必要な能力を育成し、又は教養の向上を図ることを目的とするとされていることから、専修学校における専攻科目と従事しようとする業務については、相当程度の関連性が必要とされており、大学よりは厳格に審査されます。
職歴の要件
10年以上の実務経験があれば、自然科学又は人文科学の分野に属する技術又は知識を必要とする業務に従事しようとする場合に、大学や専修学校を卒業していなくても要件を満たします。なお、この「10年以上」という期間には、関連する科目を大学や専修学校で専攻した期間も含まれます。
外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務に従事しようとする場合は、3年以上の実務経験があれば要件を満たします。実務経験とは、翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾若しくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務のことです。
また、翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、大学を卒業していれば、実務経験が不要です。
IT関連の資格を持っていると強い
法務大臣が告示で定める情報処理技術に関する試験に合格、又は資格を持っている場合は、学歴も職歴も関係なく要件を満たすことができます。
ITストラテジスト試験や第一種情報処理技術者認定試験などの日本で実施される試験だけでなく、中国やフィリピン、ベトナム、ミャンマー、台湾、マレーシア、タイ、モンゴル、バングラデシュ、シンガポール、韓国で実施される試験も該当します。
犯罪歴などの要件
過去に犯罪歴や退去強制になった経験がないかも要件としてチェックされます。犯罪歴には日本においてのものだけでなく、外国人の本国におけるものも含みます。また、交通違反による処分も含みます。犯罪歴を申告しないで在留許可を得たとしても、それは虚偽申請となり、事実が発覚した場合、罰則の対象となりますので注意が必要です。本人に聞きにくい事柄かもしれませんが、必ず確認しておきましょう。
6. 入管に提出する書類
入管に提出する書類は、誰でも共通して提出しなければならない書類と、会社のカテゴリーによって異なる書類とがあります。
共通して提出しなければならない書類
在留資格を取得する際に誰もが共通して提出が必要になる書類が以下のとおりです。
在留資格認定証明書交付申請書 1通
出入国在留管理庁のホームページにPDF版とExcel版が掲載されていますので、Excel版をダウンロードして入力していくのがおすすめです。
写真 1枚
外国人本人の顔写真です。サイズは縦4センチ、横3センチです。写っている顔の比率などが細かく規定されていますので、出入国在留管理庁のホームページで必ず確認してください。
意外と気を付けなければいけないのが、提出の日前6か月以内に撮影されたものでなければならないことです。パスポートで使用した顔写真と同じものを提出する場合、パスポートの発行年月日(DATE OF ISSUE)が6か月以前であると、写真が撮影されたのが6か月以前ということになりますので、指摘を受ける可能性が高いでしょう。
返信用封筒 1通
定形封筒に宛名、宛先を明記の上、必要な額の郵便切手(簡易書留用)を貼付したもの。申請結果の返送に使用されます。
パスポートの写し 1部
必須ではありませんが、提出することが推奨されています。
少なくとも、在留資格認定証明書交付申請書は、パスポートを見ながら記入することをおすすめします。申請書の氏名欄は、パスポートに記載のある氏名の表記と同じにしておいたほうが手続きがスムーズに進むからです。
外国人が日本大使館でビザを申請するときに、氏名の表記が違っているとビザがもらえない可能性がありますし、ビザがもらえたとしても入国手続きの際、確認に時間がかかってしまうことがあります
専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書 1通
専門学校の学歴で在留資格を取得する場合に必要です。専門学校を卒業して、専門士又は高度専門士の称号を付与された者であることを証明するためです。
申請人の派遣先での活動内容を明らかにする労働条件通知書、雇用契約書等 1通
自社で就労させるのではなく、他の会社に派遣して就労させる場合に提出が必要です。
会社のカテゴリーを証明する書類
上記以外にも提出が必要な書類があります。これは雇用する会社がどのような会社なのかを証明するための書類になります。
4つにカテゴリー分けされた分類の中で、ご自身の会社がどのカテゴリーに入るかによって、用意しなければならない書類の種類や数が異なってきます。
カテゴリー1に分類される会社は、提出する書類が一番少なくて済みます。会社の規模が大きければそれだけ信用力が高くなるためです。
1から4までのカテゴリーは以下のように分類されています。
カテゴリー1の会社が提出する書類
| 対象 | 上場企業や公共団体など |
|---|---|
| 提出書類 | ・四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(写し)
・主務官庁から設立の許可を受けたことを証明する文書(写し) など |
カテゴリー2の会社が提出する書類
| 対象 | 源泉徴収額1,000万円以上の企業 |
|---|---|
| 提出書類 | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し) |
カテゴリー3の会社が提出する書類
| 対象 | 源泉徴収額1,000万円未満の企業 |
|---|---|
| 提出書類 | ・前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(写し)
・労働条件を明示する文書 ・外国人本人の履歴書 ・大学等の卒業証明書、在職証明書、情報処理技術に関する合格証書 ・会社の登記事項証明書 ・勤務先の沿革等が記された案内書など ・直近の年度の決算文書の写し(新規事業の場合は事業計画書) |
カテゴリー4の会社が提出する書類
| 対象 | 源泉徴収額票等の法定調書合計表が提出できない企業 |
|---|---|
| 提出書類 | カテゴリー3に挙げた書類に加えて以下の書類対象
・源泉徴収額票等の法定調書合計表が提出できない理由をあきらかにする資料 ・給与支払事務所等の開設届出書の写し ・直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書 ・納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料 |
雇用理由書
必ずしも必須の提出書類ではありませんが、在留資格の該当性について補強説明をするために雇用理由書という書面を作成して提出することがあります。
外国人に就いてもらいたい仕事が、在留資格に合致していて、外国人の持つ技術や知識などの要件がそれに当てはまっていること、そして継続して雇用することができる会社であることを証明できなければ許可が下りませんので、提出が定められている書類だけでは証明できそうもない場合は、雇用理由書を提出することをおすすめします。申請書を提出したあとに入管のほうから提出を求められることもあります。所定の書式はとくにありません。
7. 入管への申請と証明書の受け取り
申請書類一式は、会社の所在地を管轄する出入国在留管理局(入管)の窓口に提出して申請します。
「技術・人文知識・国際業務」の新規申請の場合、許可が下りるまでに1~3か月かかります。入管での審査が通ると「在留資格認定証明書」が発行されますので、受け取りに行きます。受け取った証明書は本人に郵送して、現地の在外公館に持っていってもらい、ビザの発給を受けます。
また、入管への申請はオンラインですることも可能で、その場合は「在留資格認定証明書」をメールで受け取ることができます。本人にも証明書をメールで送ることができるため、とても便利です。
8. 採用から入社までの流れ
ここまで、細かい手続きについて見てきましたが、採用から入社までの流れをざっくり確認しておきましょう。
本人が外国にいる場合
- 採用決定
- 雇用契約締結
- 会社が「在留資格認定証明書交付申請書」を入管へ提出
- 入管が審査 → 証明書発行(許可が下りる)
- 会社は証明書を本人に送付
- 本人が現地の日本大使館・領事館でビザ申請
- ビザ発給後、来日・入社
本人がすでに国内にいる場合(留学生など)
- 採用決定
- 雇用契約締結
- 「在留資格変更許可申請」を入管へ提出
- 許可されれば就労可能に
9. 書類準備から証明書発行までのスケジュール感
書類の作成から証明書が発行されるまでのスケジュール感は以下のような感じになります。
| 書類準備~申請まで | 2~4週間 |
|---|---|
| 入管での審査 | 1~3か月 |
通常は来日の3か月前からしか申請できませんが、3月に大学等を卒業して4月から入社を予定している場合、前年の12月から申請を受け付けてもらえます。4月に入社予定で来日する外国人はとても多く、毎年この時期は入管への申請が混み合いますので、4月の入社に間に合うよう、早めに準備を始めて提出することをおすすめします。
なお、認定証明書の有効期間は3か月間ですので、発行から3か月以内に入国しないと証明書の取り直しが必要になりますので注意が必要です。
10. 申請することができる人
入管に申請することができるのは以下の人です。
- 本人
- 雇用する会社の職員
- 申請取次者(申請取次行政書士または弁護士)など
原則として本人が申請するものではありますが、本人が来日する前に申請する必要があることを考えると、雇用する会社の職員が代理して申請するのがスムーズです。
11. 専門家に依頼することで許可率が上がります
在留資格の審査は、入管による裁量が大きく、所定の書類を提出したからといって通るとは限らない世界です。
適切な在留資格を、確実に、早く取得することが社内において求められるプレッシャーの中で、入社までのスケジュールを管理しながら、間違いなく書類を作成していくことはなかなか難しい場面もあるかもしれません。
この記事が、採用活動の一助となれば幸いですが、もし手続きに少しでも不安を感じたり、本業に集中するために煩雑な手続きを任せたいとお考えの場合は、入管業務の専門家である行政書士に相談してみることもご検討ください。
当事務所では、最新の法改正や入管の審査傾向を踏まえ、最もスムーズかつ確実な方法でビザ取得手続きを進めさせていただきます。
相談は無料で承っております。相談してみた結果、「やはり自分でやることにした」「他の事務所に頼むことにした」となっても大丈夫です。あとからお電話やメールで勧誘することもありませんので、安心してご相談ください。
貴社が優秀な外国人材を迎え入れることができ、ますます発展されますことを心よりお祈り申し上げます。
★外国人を雇用したあとの管理については、こちらの記事もあわせてご参照ください。
【解説】外国人を雇用するとき知っておきたい管理上の注意点は?