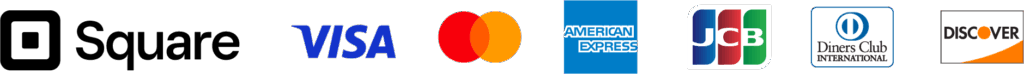外国人材の採用は、今や多くの企業にとって事業成長に不可欠な戦略となっています。多様なバックグラウンドを持つ社員が社内にいることは、組織の活性化にも繋がります。
しかし、その一方で、人事・総務担当者の方々が日々直面しているプレッシャーやリスクについては、あまり語られることがありません。善意に基づいて採用し、誠実に雇用しているつもりでも、複雑な入管法のルールによって、気づかぬうちに法的なリスクを抱え込んでしまうケースが後を絶たないのです。
この記事は、脅しや不安を煽るためものではありません。しかし、実際に多くの企業が陥ってしまった事例を基に、担当者が見落としがちな「在留資格管理の落とし穴」を具体的に解説します。この記事を読み終えたとき、貴社の管理体制をもう一度、専門家の視点で見直す必要性を感じていただけるはずです。
目次
1. 在留期限切れという「時限爆弾」
これは最も基本的かつ、最も深刻なリスクです。
「分かっているよ」という声が聞こえてきそうですが、本当に恐ろしいのは、その発生原因の多様さです。
・担当者の多忙による単純な確認漏れ
・従業員本人からの報告遅れ
・更新申請はしたものの、書類の不備で受理されていなかった
理由が何であれ、在留期限を1日でも過ぎればその従業員は「不法残留(オーバーステイ)」となり、会社がその状態で働かせ続ければ「不法就労助長罪」という罪に問われかねません。
誰が罰せられるのか?
不法就労は、外国人本人が退去強制になるリスクがあるだけでなく、させた側の企業にも罰則があります。具体的には、代表取締役、人事担当役員、そして現場の担当者自身が処罰の対象となり得ます。「知らなかった」「本人に任せていた」という言い訳は通用しません。罰則は「3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金」です。
経営へのインパクト
たった一人の在留期限切れが、企業の信用を失墜させ、その後の外国人採用計画全体に悪影響を及ぼす可能性があります。特に技能実習生や特定技能外国人を雇用している企業の場合、管理体制の不備を指摘され、今後の受け入れが一切できなくなるという最悪のケースもありえます。
Excel管理の限界
従業員が数名ならまだしも、10名、20名と増えてくると、手動のExcel管理ではヒューマンエラーのリスクが飛躍的に高まります。これは担当者の能力の問題ではなく、「仕組み」の問題なのです。
2. 「許可された活動」の範囲外という見えざる境界線
雇用している外国人社員一人ひとりの「許可された活動内容」を、その根拠となる申請書類のレベルで正確に把握していますか?
在留カードに「就労可」と書かれていれば、どんな仕事をさせても良いわけではありません。在留資格は、許可された「活動範囲」と固く結びついています。これこそ、多くの企業が意図せず法令違反を犯してしまう、最大の落とし穴です。
違反になりうるケース
あなたの会社では、「良かれと思って」の以下のような業務指示をしていませんか?
ケースA:ITエンジニアを、繁忙期に工場ラインへ
(状況)
「技術・人文知識・国際業務」ビザを持つITエンジニア。人手が足りないため、製造ラインでの検品や梱包作業を2週間手伝ってもらった。
(法的リスク)
これは「単純労働」と見なされ、在留資格で許可された「技術(理学・工学の知識を要する業務)」の範囲を逸脱します。たとえ本人が同意していても、善意の手伝いであっても、不法就労と判断される可能性があります。
ケースB:翻訳担当者を、店舗のレジ・接客へ
(状況)
「国際業務」として採用した翻訳担当者。語学が堪能なため、人手が足りない系列の小売店で、販売・レジ業務をメインで行わせた。
(法的リスク)
主たる業務が明らかに翻訳ではなく販売・接客に移った場合、許可された活動範囲からの逸脱となります。インバウンド対応という側面があったとしても、業務の大部分が単純労働と見なされれば違法です.
ケースC:ALT(英語指導助手)が、学校外でアルバイト
(状況)
「教育」ビザで働くALT。週末に個人の語学教室で英語を教えて収入を得ていた。
(法的リスク)
「教育」ビザは、許可された学校での教育活動に限定されています。それ以外の場所で報酬を得る活動をするには「資格外活動許可」が必要です。この許可なく行えば、不法就労となります。
3. アルバイト留学生の「28時間ルール」という聖域
飲食業や小売業などで多くの戦力となっている留学生アルバイト。彼らの「資格外活動許可」は、原則として「週28時間以内」という絶対的なルールの上に成り立っています。
見落としがちなルール
「うちの店で28時間」ではない
このルールは「すべてのアルバイト先の合計時間」です。採用時に「他のお店でも働いていますか?」と確認し、合計時間を管理する義務が雇用主にはあります。確認を怠り、結果的に合計28時間を超えて働かせてしまった場合、雇用主も責任を問われます。
長期休暇中の「週40時間」の罠
学校の夏休みなどの長期休暇中は、週40時間まで労働が可能です。しかし、「授業がないから長期休暇だろう」と安易に判断するのは危険です。大学などが定める正式な学則上の長期休暇期間であることを、ポータルサイトの通知などで客観的に確認する必要があります。
業種の制限
留学生は、パチンコ店やゲームセンター、バーやスナックなど、風俗営業関連の店舗では一切働くことができません。たとえ清掃の仕事だけだとしても禁止されています。これも「知らなかった」では済みません。
4. 転職時に忘れがちな「届出義務」という小さな綻び
手続き上の小さな義務であっても、怠ると後々大きな問題に発展しかねません。
本人の義務でも会社のリスクに
「技術・人文知識・国際業務」などの就労ビザを持つ外国人が、会社を退職した時、または新しい会社に入社した時、本人は14日以内に入管に届け出る義務があります。この届出は本人の義務ですが、会社側も「中長期在留者の受け入れに関する届出」を出すことになっています。
管理体制への不信感
届出を怠った事実が、その後のビザ更新時に発覚した場合、「この会社は外国人雇用の管理体制が杜撰(ずさん)なのではないか」と入管審査官にマイナスの心証を与えかねません。
次の更新への影響
たとえ転職した本人に悪意はなくても、この届出忘れが原因で、次回の更新申請が通常より慎重に審査されたり、場合によっては不許可の一因となったりすることがあります。小さな綻びが、会社の採用計画全体を揺るがすリスクになるのです。
5. 「本人に任せきり」という最も危険な管理体制
これまで挙げてきた落とし穴の、すべての根源にあるのがこの問題です。
「ビザは本人の問題だから」「分からないことは本人が入管に聞けばいい」
このスタンスは、一見合理的のようですが、企業としてのリスクマネジメントを放棄していることに他なりません。従業員本人は入管法の専門家ではありません。悪意なく間違いを犯したり、手続きを忘れたりすることは十分にあり得ます。
外国人材という貴重な「資産」を、管理不行き届きという「リスク」に晒しているのは、他ならぬ会社自身の管理体制なのです。
6. まとめ
ここまでお読みいただき、もしかしたら、いくつかの項目で「ヒヤリ」とされた担当者の方もいらっしゃるかもしれません。
しかし、これらのリスクは、正しい知識を持ち、適切な管理体制を構築することで、すべて予防することが可能です。在留資格管理は、単なる事務手続きではありません。それは、外国人社員が安心してパフォーマンスを発揮できる環境を整え、彼らを会社の貴重な「資産」として守り育てるための、攻めのリスクマネジメントです。
「では、まず何から始めればいいのか?」
「自社の管理体制に、具体的にどんな穴があるのか知りたい」
そう思われたなら、ぜひ一度、専門家による客観的な診断を受けてみることをお勧めします。
当事務所では、相談を無料で承っております。相談してみた結果、「やはり自分でやることにした」「他の事務所に頼むことにした」となっても大丈夫です。あとからお電話やメールで勧誘することもありませんので、安心してご相談ください。